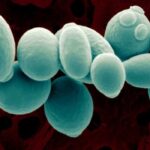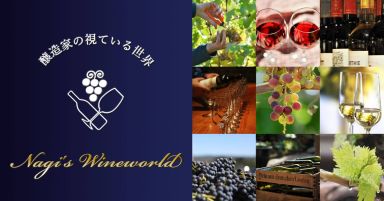ワインの熟成は、その味わいを深める重要な要素です。一般的には酸化熟成によってワインは変化していきますが、醸造段階では、酸化とは異なる「生物学的熟成」という手法が用いられる場合もあります。生物学的熟成とは、産膜酵母と呼ばれる酵母を利用した熟成方法です。産膜酵母は樽やタンクで保管中のワインの液面に膜を形成し、独特の風味を生み出すことでワインに新たな表情を与えます。
スペインのシェリーやフランスのヴァンジョーヌなど、個性的な味わいを特徴とするワインでは、この産膜酵母を活用することによってその風味を獲得しています。これらのワインに用いられる産膜酵母の中でも、特に「フロール (flor yeastもしくはflor velum yeast)」と呼ばれる酵母が、生物学的熟成における中心的役割を果たしています。本稿では、フロール酵母の生態とワインへの影響について解説していきます。
※ 注意: 産膜酵母の中には、ワインに悪影響を与えるものも存在します。それらについては、別の記事で詳しく解説しています。
ワインの個性が台無しに!産膜酵母ってなんだろう?
産膜酵母を理解する:ベラムとフロール
「産膜酵母」とは、木樽やタンクなど容器内で保管中のワインの表面に白い膜を形成する酵母のことです。この膜は「フロール (flor)」や「ベラム (velum)」と呼ばれます。本稿では、シェリー酒やヴァンジョーヌ酒の製造に用いられる産膜酵母を「フロール酵母」、膜自体を「ベラム」と呼びます。
気液界面にベラムを形成する特性を持つ酵母は、実は多く存在します。醸造酒のアルコール発酵で広く利用される Saccharomyces cerevisiae (サッカロミセス セレビシエ) をはじめ、非サッカロミセス系の酵母にも、この特性を持つ株が見つかっています。
そうしたなかで、シェリー酒やヴァンジョーヌ酒に使われるフロール酵母の株はそのすべてがSaccharomyces cerevisiae に属する株から構成されています。つまりフロール酵母は、ベラムを形成する特性を持つ Saccharomyces cerevisiae 株の総称といえるのです。
産膜酵母を使った醸造手法はそこまで一般的なものではありません。そのため、フロール酵母はなにか特別な種類の酵母のように思われがちです。しかしフロール酵母は、多少の違いはあるものの、基本的にはブドウの果汁をワインに変えるために必須の酵母である Saccharomyces cerevisiae と同じ種類の酵母なのです。
遺伝子解析が明らかにするフロール酵母の正体
シェリー酒やヴァンジョーヌ酒の製造に欠かせないフロール酵母ですが、どのような方法で醸造工程中に入ってきているのか、その詳細はまだ完全には解明されていません。フロール酵母はアルコール発酵で使われるSaccharomyces cerevisiaeと同じ種類の酵母であるため、アルコール発酵後にも生存した酵母がフロール酵母になるという説明がされることもあります。しかし現在のところ、その可能性はあまり高くないと考えられています。
フロール酵母と通常のアルコール発酵に使用されるサッカロミセス系の酵母は、遺伝子型によって簡単に区別できます。フロール酵母は複数の酵母株から構成されていますが、それらをフロールとしてまとめているのが、FLO11と呼ばれる遺伝子です。基本的にはこの独特な遺伝子を持つ Saccharomyces cerevisiae 株を総称してフロールと呼んでいます。
フロール酵母は必ずFLO11を遺伝子型として保有しています。そのため、ワイン醸造中のいずれの時点であっても、酵母の遺伝子検査を行うことでそこにフロール酵母が存在するのかどうかを知ることができます。これまでの検証結果では、アルコール発酵中や発酵直後のワインからは、FLO11を遺伝子型にもった酵母は検出されていません。フロール酵母は、熟成のためにワインを樽に移動した後ではじめて、ワイン中に存在が確認されています。
このことから、フロール酵母は通常のアルコール発酵を担っているサッカロミセス セレビシエから連続的に移行した存在ではなく、熟成に利用される樽をはじめ、なんらかの外的要因を経てワイン中に入ってくる存在である可能性が高いと考えられます。
複雑な要因が絡み合う遺伝子の発現
一方で、FLO11の発現には複雑な要素が絡み合っていることが分かっています。例えばグルコースなどの発酵性糖分はこの遺伝子の発現を抑制する因子の一つです。FLO11の発現にはそれ以外にも複数の条件があり、解糖でのエネルギー獲得から呼吸でのエネルギー獲得へと切り替わるDiauxic shiftをきっかけにこの遺伝子が発現する可能性も、まだ完全に否定されたわけではありません。
なお、仮にDiauxic shiftによりアルコール発酵を行っていた酵母がフロールに移行するとしても、すべての Saccharomyces cerevisiae株がFLO11を保有しているわけではありません。ある検証事例では、該当遺伝子の保有率はおよそ50%程度であったことが報告されています。
ベラム形成とフロール酵母の浮力
ベラムはなぜ気液界面、つまり液面に形成されるのでしょうか?答えは単純で、フロール酵母が浮くからです。しかし、なぜフロール酵母が浮くのか。そのメカニズムは少し複雑です。
フロール酵母は細胞の密度が低いために浮いているわけではありません。繰り返しになりますが、フロール酵母は基本的にはサッカロミセス属の酵母です。通常、アルコール発酵を行っている最中に果汁中に大量に存在するこれらのサッカロミセス属の酵母が液面に浮いてきて膜を張るようなことはありません。発酵中に勢いよくあがる発酵ガスによって持ち上げられてくるだけです。発酵が落ち着けば、それらの酵母はすぐに沈んでいきます。浮力はサッカロミセス属の酵母のなかで、フロール酵母だけが持つ特徴といえます。
フロール酵母の大きな特徴である浮力は、フロール酵母をフロール酵母たらしめている遺伝子、FLO11に由来しています。FLO11が発現することで酵母の細胞表面の疎水性が高くなります。また同時に、細胞同士をつなぎ合わせる接着剤のような成分が作られ、多細胞凝集体の形成が促進されます。この凝集体の内部に残留糖によるアルコール発酵で発生した炭酸ガスがとらわれることで浮力が供給され、気液界面まで浮上し、さらに連結することでベラムを形成するのです。
フロール酵母の浮力、より具体的にはその根本にある疎水性の強さは一定ではなく、それぞれのフロール酵母の遺伝子型とワインの状況によって変化することが分かっています。細胞表面の疎水性が強く、それによってより大きな浮力を得たフロール酵母ほど、形成するベラムの厚みも厚くなる傾向を示すと考えられています。
生物学的熟成:フロール酵母がもたらすワインの変容
フロール酵母を利用した生物学的熟成は、ワイン醸造手法として特殊な位置づけにあります。なぜこのような特殊な手法を用いるのでしょうか。
歴史的な発祥理由は別として、産膜酵母を利用したワインのスタイルが1つのジャンルとして確立されている現在では、フロール酵母の代謝によって得られる独特な風味や香りを目的としています。
フロール酵母によって気液界面にベラムが形成されたワインでは、フロール酵母は酸化的な代謝を行う一方で、ワインそのものは酸化から守られた状態となります。例えばワインの色味が茶褐色に変化する褐変と呼ばれる変化は、ワインにおける分かりやすい酸化の目印です。一方で、ベラムが形成されたワインでは、こうした褐変が起きないことが報告されています。このように、ワインがもっとも嫌う酸化から守られつつ、フロール酵母が行う代謝によってワインは熟成の度合いを深めていきます。
フロール酵母によるワインへの影響の度合いは、フロール酵母の株の種類やベラムが形成されるワインの状態によって大きく異なります。しかし、エタノールの酸化に伴うアセトアルデヒドの増加、グリセロール、酢酸、そしてアミノ酸類の減少などは、ほぼ一貫して確認されている、フロール酵母によるワインへの影響です。
こうした各種の影響が、ワインの香りや味わいを中心にワインの持つニュアンスを変え、シェリーやヴァンジョーヌに独特の特徴をもたらしています。
生物学的熟成によるワイン組成の変化:代謝と生成のバランス
生物学的熟成は、ワインの組成に様々な変化をもたらします。ベラムが形成されたワインではそこに含まれている成分の変化の方向は、大きく分けて3つに分類されます。
- 代謝によって含有量が減少する成分
- 生成によって含有量が増加する成分
- 影響を受けず、含有量が変化しない成分
代謝によって減少する成分
エタノール(アルコール)は、生物学的熟成によって含有量が減少する代表的な成分の1つです。長期間の生物学的熟成を行うことで、ワインのアルコール度数は徐々に低下していきます。シェリーの場合、原産地呼称統制法によって最低アルコール度数が15%と定められているため、これ以下になるほどの長期にわたる生物学的熟成は一般的には行われません。
グリセロールもまた生物学的熟成を経てその含有量を大きく減らす物質です。エタノールよりも多く代謝されます。グリセロールは粘度の高い、甘みを持つ成分で、ワイン中ではアルコール発酵時に酵母の代謝によって生成されます。つまり発酵時に酵母が作り出したものを、熟成時に酵母が消費していることになります。フロール酵母によるグリセロールの代謝は、ワインの味わいと粘度、口当たりに変化をもたらす可能性があります。
酢酸は腐敗果などを通した酢酸菌の混入や、その他の微生物の影響によってワインに含まれることがあります。酵母も微量ながらアルコール発酵中に酢酸を生成することがあります。
酢酸はワインの品質にとってネガティブな要素の一つであり、含有量の上限が法的に規制されている国や地域もあります。一般に、ワインに含まれてしまった酢酸は通常の方法では除去できません。法的規制に抵触するほど多量に含まれてしまった場合、タンク全量を破棄せざるを得なくなる場合もあります。
酢酸によるワインの汚染は、アルコール発酵後の熟成期間中に生じることがあります。しかし、フロール酵母は酢酸を代謝することができるため、ベラムを用いた熟成では、酢酸含有量を低く抑えることができます。
生成によって増加する成分
アルコールやグリセロール、酢酸がフロール酵母の代謝によって含有量が減少する一方で、アセトアルデヒド、アセトイン、酢酸エステルを含む複数の高級アルコール類は生成によって含有量を増加させます。特に熟成香や酸化香を特徴付ける成分の一つであるアセトアルデヒドの生成量は非常に多くなる傾向があります。一般的な生物学的熟成後のワインでは熟成前の3~4倍程度の含有量ですが、多いときには7~8倍にものぼることが報告されています。
フロール酵母を用いた熟成における課題
フロール酵母を用いた熟成は、ワインに独特なニュアンスをもたらすだけでなく、ワインに含まれる一部の成分の含有量を減らすなど、醸造場にとってメリットと考えられる効果をもたらします。しかし、一方で課題として認識すべき点もいくつかあります。
アセトアルデヒド生成量の予測困難性
フロール酵母を用いた熟成では、アセトアルデヒドの生成量が多くなる傾向があります。アセトアルデヒドはアルコールを分解する過程で生じる化合物です。このため飲酒後に体内でも生成されますが、そうして生成されたアセトアルデヒドを分解するための酵素を体内に持たない場合には二日酔いや頭痛などの原因となることがあります。
人体に対して有毒性を示すアセトアルデヒドですが、生物学的熟成の過程においてどれだけの量が生成されるかを事前に知ることは困難です。これはアセトアルデヒドに限らず、フロール酵母の代謝に関わる物質全般において同じことが言えます。
フロール酵母の挙動の不均一性と再現性の課題
アルコール発酵に用いるサッカロミセス属の酵母の場合、事前に選抜された乾燥酵母を使用することで、ある程度の発酵挙動や発酵生成物を予測できます。しかしフロール酵母の場合、通常そのような事前選抜された酵母を使用することはなく、ベラムを形成している酵母がどの株によるものなのかが正確には分かりません。さらに、同じ菌株であっても形成するベラムの形態学的特徴が異なる場合が多くあることが報告されています。つまり、同じ株のフロール酵母であってもまったく異なる挙動を示す可能性があるのです。
こうした不確実性が高いことから、フロール酵母を用いた熟成で再現性を持たせることは容易ではありません。シェリーの製造で採用されているソレラシステムは、複数の樽の中身を何度も混ぜ合わせることで、こうした品質的不安定性を解消するための手段として機能しています。
ベラム形成の不安定性
フロール酵母の増殖は、微生物の生存環境としては極めて過酷な状況で行われています。そのため、菌株によってはベラムが形成されない場合もあり得ます。生物学的熟成においてワインが酸化から守られるのはベラムによってその液面が覆われているからです。ベラムが形成されない場合、ワインが酸化から守られず、品質上致命的なダメージを受けてしまう可能性も出てきます。
フロール酵母を用いた熟成には確かにメリットがありますが、一方で安易に手を出しづらいデメリットも存在しているのです。
ワイン造りに、あなたらしさを活かすパートナーを
栽培や醸造で感じる日々の疑問や不安を解消し、ワインの品質をさらに高めたい──
Nagi Winesは、あなたの想いとスタイルを尊重しながら、すべての工程をともに歩みます。
経験豊富な専門家が現場に入り、知識・技術・品質の向上を、実地作業を通じて支援。
費用を抑えつつも、あなたのワインらしさを守りながら確かなフォローを行います。
まずはお気軽にご相談ください。
産膜酵母の利用の拡大
従来、ワイン醸造において産膜酵母を積極的に利用するケースは多くありませんでした。フロール酵母を積極的に活用してきたシェリーやヴァンジョーヌは全体からみれば例外というべき存在です。しかし近年、産膜酵母を醸造に取り入れる事例が増加してきています。これまで産膜酵母を使用していなかった産地においても、通常のスティルワインの熟成にこの手法を採用する造り手が出てきています。
新たに熟成に産膜酵母を用いる取り組みの多くは、ナチュラルワインの枠組みのなかで進められています。ワインの熟成中に産膜酵母を発生させることで、ワインを酸化から守りつつ微生物安定性を高め、結果として亜硫酸の添加量を削減しようとするのがその考え方です。このような取り組みは従来のフロール酵母の利用目的とは少し異なっています。
ワインの安定化のために産膜酵母を応用しようとする考え方には一理あります。しかし、同時に簡単には受け入れられない側面もあります。その最大の理由は、ベラムを形成している酵母がどのような存在なのかが不明確であることです。
シェリーやヴァンジョーヌといった歴史的にみても長期にわたってフロール酵母を活用してきた伝統産地でさえも、そのフロール酵母がどこから醸造工程中に入ってきているのかが正確には分かっていません。さらに、産膜する存在にはフロール酵母とは異なる、雑菌に分類される類いの微生物も含まれます。ベラムを形成したからといって、そこにいるのがフロール酵母であるとは限りません。
こうした状況において、これまでフロール酵母を使用していなかった場所でいきなり産膜酵母を導入しようとしても、それが正しくフロール酵母である可能性には疑問が残ります。仮にそれが雑菌であってもベラムを形成するのであればワインは酸化からは守られるかも知れません。しかしその一方で、そうした細菌が望ましくない代謝をはじめてしまえばワインの品質は著しく低下することになります。
フロール酵母の分野においても乾燥酵母のように、予め性質の分かっている菌株を確実に他所に移行できる技術の検討が進められています。フロール酵母自体その挙動に不均一性がみられ、使用した結果が安定しない存在ではあります。しかし、それでも由来や性質の分かっている菌株を使用することで、少なくともベラムを形成する一方で致命的な代謝を行う雑菌の繁殖を許してしまうような事態の減少が期待されます。