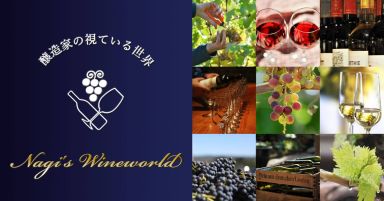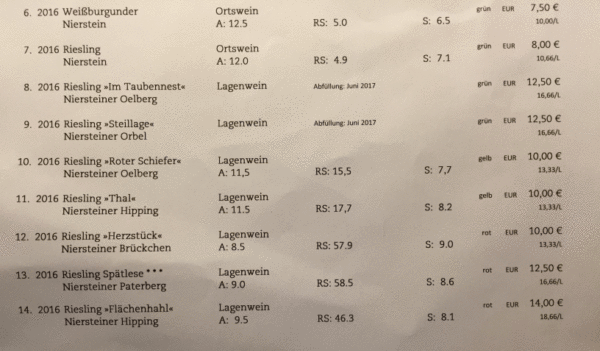
今日はNiersteinで行われた、2017年の新酒お披露目のイベントにお手伝いで参加してきました。
普段から触れることの多いラインガウのワインと比較して、明らかに酸の出方の違うこの産地のワインを知ることはリースリングをはじめとした各種品種の違いを知る上でとても興味深いものでした。
ところで、この手のイベントでワイナリーの訪問すると必ずといっていいほど目にするのがワインリストです。このワインリスト、ワイナリーさんごとの考え方というか受け止め方がよく出ていて、たくさんの情報を載せているところもあればワインの名前と価格だけを載せているところもありと、それぞれの個性をおもわせます。みなさん、このワインリスト、どのような視点で見ているでしょうか?
ワインリストの情報はワインを分析する大きな助け
ワインを楽しむことだけを考えれば、アルコール度数はともかくとしても別に残糖度や総酸量を知る必要はないと思います。単に飲んで美味しいか美味しくないかを判断するのであれば、これらの情報は不要だからです。一方で、分析的にワインを飲むことをしたいのであれば、これらの情報は必須でしょう。
そして、一個の醸造家としてワインリストを見る時には、やはりアルコール度数、残糖度、総酸量の情報は最低限欲しいところです。
なぜかといえば、これはあくまでも筆者の例ですが、アルコール度数と残糖度を見ることで収穫時の大体のブドウの糖度を判断するからです。そこに総酸量を加えて考えることで、収穫されたブドウの熟度がある程度の範囲で仮定されます。そのうえで、その仮定された熟度の状況からその年の状況を連鎖的に読み取っていくわけです。
もっとも筆者は醸造家なので、甘い酸っぱいといった味の方向の想像ではなく、あくまでもそのような味のバランスにした醸造的な理由を想像していくのですが。
[Ad-innen]
ワインリストから醸造の根拠を探る
ワインリストを単なる価格表として見ている方はまだまだ多いような気がします。
しかし、ワインリストに記載された情報からある程度の予測をもってワインを見ていくこともまた可能なのです。もちろん、最終的には実際にそのワインを口に含んでみて、自分の受け止め方でもってそのワインを判断することが絶対的に必要ですが、どうしてそのような醸造をしたのか、そのような結果を出すためにどのような方法をとったのかを考える、思考的冒険をワインリストはさせてくれます。あまり一般的ではないですし、ほとんどの方にはまったくといっていいほど必要ないワインリストの読み方だとは思いますが、ワインリストは単に価格を知るためのものではないんだということも知っておいてほしいと思います。