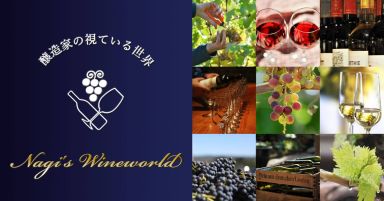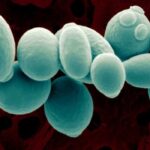ワインの味わいに重要とされる要素にはいろいろありますが、そうした中であなたは酵母を何番目に重要な存在としてあげるでしょうか?
ワイン醸造において酵母はとても重要な役割を担っています。そのことは誰もが認めているものの、ワインの味わいにおける位置づけという話になると途端に意見が分かれます。これには乾燥酵母と野生酵母の、ある意味で対立的な関係性が関わっています。
例えば気候。例えば土壌。例えば地形。こうしたものは半ば、その場所に紐付けられた固定のもので、代替するものがありません。その土地でワインを造ろうとするならば、それらの存在は受け入れる以外に選択肢がありません。手を加えるにしてもそれは大がかりなもので、自由度は決して高くはないものです。それに対して、酵母は事情が少し違います。酵母だけは、選択肢が無数に用意されています。
そうしたことから、酵母はテロワール (Terroir) の要素に入れられることもあれば、入れられないこともあります。一般にテロワールという概念には土地との不動の結びつきや土着性を求めるため、土地から浮いて選択肢が用意された酵母はテロワールの概念には合わないという考え方も一部には根強く存在しています。
そうしたテロワール思想の中で重要視されるのが、野生酵母の存在です。
ヒトの手を介したものではなく、その土地に存在している野生の酵母であれば、テロワールの思想にも合致した重要な構成要素の1つになり得る、というわけです。
現在、商業的に製品化されている乾燥酵母もその由来は自然界にいた、野生の酵母です。しかしその存在は現代において、野生の酵母とは区別して、まるでまったく別の存在であるかのように語られています。その原因の1つは、野生の酵母がどのようなものであるのかに対する理解の不足です。この記事では、普段あまり語られることのない酵母の由来、そして野生酵母という存在の位置づけについて解説していきます。
酵母の歴史
ヒトにとっての酵母の歴史とはそのまま、ヒトと発酵食品との関わりの歴史に他なりません。
現在分かっている範囲では、紀元前7000年頃、今の中国ではすでに発酵飲料が生産されていたとされています。ここから進むこと1000年ほどでイラン近郊で、さらにそこから3000年ほど経ってエジプトでそれぞれワインが造られはじめたとされています。
ワインといえばヨーロッパの印象が強い一方で、ヨーロッパ大陸でワインが造られはじめるのは比較的時代を下ってからのことです。紀元前2000年のギリシャを皮切りに、紀元前1000年にイタリアで、そして紀元100年頃に北欧でワイン造りが行われるようになったと言われています。アメリカにワイン造りが渡ったのは西暦1500年頃のことです。
この長い年月、酵母は常にヒトに近いところに存在し、ヒトの移動に伴って移動と地理的拡散をしてきたと考えられています。
ワイン用酵母は中東生まれ
自然界には無数の酵母が存在しています。そのなかにはヒトの生活に強く関わっているものもいれば、まったく関わりをもっていないものもいます。それらの酵母はいくつかのグループに分類され、そうしたグループの1つにワイン関連酵母のグループが形成されています。
ワイン関連株のなかでも特にサッカロミセス系の酵母は複数回の分化を通して形成されたことが遺伝子解析の過程で明らかになっています。そのグループを形成する菌株の多くはレバノン株と呼ばれる株由来の遺伝子を基部に持ち、メソポタミアに起源を持っていることが分かってきています。
メソポタミアで生まれたこの酵母は、その後に地中海に面した地域に拡散したグループと、中央ヨーロッパに拡散したグループに分かれていったと考えられています。
それぞれの酵母の関係性
ワインの発祥を巡る議論のなかではしばしば、ビールの生産が歴史的に先にあり、これを模倣する形でワインが造られはじめた、と言われます。しかし、それぞれに使われている酵母の遺伝的特徴を見ていくなかで、実はそうでもないらしいことが分かってきています。
ビールの発酵を担う酵母の遺伝子群と、ワインの発酵を担う酵母の遺伝子群の間にはかなりの「距離」があることが遺伝子解析を通して判明したからです。この両者は遺伝的に見て別物であり、どちらかの酵母を利用する技術が先にあって、その応用で、つまりその酵母を利用してもう一方の生産に着手したわけではないらしいことが分かったのです。
むしろこの遺伝的に異なるビール酵母とワイン酵母の間を埋めるのが、パン用酵母であるらしいことが分かっています。さらに日本の清酒酵母の遠いご先祖さまはどうやらこのパン用酵母であるらしいことも指摘されています。
野生酵母の遺伝的多様性
テロワールの構成要素として酵母を含めるとき、そこに期待されるのはその土地独自の特性を持った酵母の存在です。これは、その土地でしか観察されない遺伝的特徴と言い換えることが出来ます。
一方で酵母、特にサッカロミセス属の酵母の進化の歴史を調べていくと、そこには家畜化の影響が色濃く見られます。
現在、ワイン醸造に使われている酵母の多くはそれが乾燥酵母によるものであろうと自然発酵によるものであろうと、サッカロミセス系に属しています。最近は非サッカロミセス系酵母の利用も増えてきてはいますが、発酵というプロセス全体を通して俯瞰すれば、やはりサッカロミセス系酵母を抜きにワインの発酵を終えることはほぼありません。そしてこのサッカロミセス系酵母の特徴とされているのが、エタノールや亜硫酸、銅に対する高い耐性です。
ワイン用の酵母群は遺伝的に見て比較的多様性の豊富な集団とされています。しかしそうした多様性のなかにあっても、上記の耐性はほぼ一貫して保持されています。これは長い時間をヒトの生活に寄り添って重ねたことによる家畜化の影響と考えられています。ヒトが決まった用途に使い続けた結果、酵母の側もその環境に適応した進化を遂げたのです。
土地に依存しない酵母
例えばパン用の酵母は地理的な関連性を強く持っているとされています。テロワールとしての酵母を期待する上では、ワイン用の酵母もこれと同様であることが望ましいのですが、実際にはそうではないことが分かっています。ワイン用の酵母群は地理的依存性が低いのです。
これまでの研究から、世界中から採取されているワインに関わるS.cerevisiaeの主要系統は3~5種に集約されることが報告されています。それぞれの系統には亜集団が形成され、そうした亜集団間の交雑も生じていることが確認されています。このため酵母の菌株としての数は多くなりますが、元をたどればその起源は狭く、ほとんどの酵母が近親関係にあることが分かります。とある調査報告に寄れば、ワイン用酵母の地理的起源による遺伝的変動は、変動全体の28%程度にしかならないとされています。
一方で興味深いのが、起源的には集約され、地理的変動幅も小さいとされるこの酵母群においても依然として遺伝的多様性は高い水準に保たれている点です。
ある地域内で酵母を採取してその分布を調査したところ、もっとも存在数が多いとみなされる代表的な菌株であってもその地域占有率は60%程度でしかないことが分かりました。またそうした分布はおおよそ100km圏内ほどごとに異なっていることも報告されています。
これはつまり、その土地に由来を持つ酵母は少ない一方で、入ってきた酵母間では比較的頻繁に遺伝的な交雑が生じていることを意味しています。
酵母の拡散と変化を担うベクターの存在
世界には数系統の、相当程度に均一化の進んだ菌株しか存在していないという事実は、同じ系統の酵母が世界中に拡散していった事実を示しています。しかしその一方で、酵母は自分で移動することはできず、その移動にはかならず移動を仲介するベクターの存在が必要となります。
酵母の移動を担ったもっとも大きな存在はヒトです。ヒトは自分たちの生活圏を拡大する過程で、それまでに培ってきた食文化を伴って移動していきました。そして、そうした移動にはその食文化を支える存在として、酵母の移動も欠かせませんでした。
ヒトに伴って移動した先で、さらに酵母の生息域を広げたのが鳥や昆虫です。これらの存在は一定範囲の地域内における短期的な酵母の拡散を担っただけではなく、さらに別の側面からの酵母のベクターとしての役割を担っています。
ハチとともに越冬する酵母
例えばワインの中やそのための容器の内側などに生きていた酵母であれば、年間を通して生存する可能性は高くなります。一方で、ヒトによって連れられていった先の自然の中で生存しようとする酵母は事情が異なります。越冬する手段がないのです。
ワイン醸造における自然発酵は、ブドウの果皮表面に付着した酵母がブドウと一緒に醸造所内に持ち込まれ、そこで活動することで生じていると説明されます。ここで端的に説明されているとおり、酵母はブドウの果皮表面に圧倒的に多く棲息しています。なぜならそこに餌となる糖があるからです。
酵母は微生物であり、その生存には餌となる存在が欠かせません。では、秋になって熟したブドウの表面に棲息している酵母は、ブドウがまだ実っていない時期にはどこにいるのでしょうか。
その一部は土壌中などに棲息していることが分かっています。しかし酵母の生息場所はそれだけではありません。スズメバチもまた、有力な酵母の保有者であることが分かっています。
スズメバチの腸内には複数の酵母が棲息していることは以前から知られていました。そうした腸内の酵母の分布を調査したところ、腸内に棲息する酵母群のおおよそ4%がS.cerevisiae系の酵母であることが分かりました。採取された17株のS.cerevisiae系酵母のうち、10株がワインの醸造に関係することのできる株であったことも報告されています。
またこの調査では、酵母群の構成はブドウの成熟期などに合わせて変化し、菌株数にも増減が生じること、その一方でS.cerevisiae株に関してはそうした変動が年間を通して少なく、季節に左右されずに安定して腸内に存在していること、そしてそうした腸内酵母の環境は女王バチからその子孫に継続していくことが合わせて確認されています。
秋から春にかけての自身での生存が難しい時期をスズメバチの腸内で越冬した酵母は、その後のハチの採餌行動に合わせて拡散していきます。こうした拡散の範囲は、ハチの行動範囲との関係から、おおよそ10km範囲程度であると推測されています。
酵母の変化を担うショウジョウバエ
ブドウの栽培においても醸造においても厄介な存在として扱われるショウジョウバエですが、実は酵母の地域的な多様性に小さくない影響を与える存在であることが分かってきています。ショウジョウバエは1世代辺りの生存期間が短く、ハチのように体内に取り込んだ酵母を越冬させるベクターとしては機能できない一方で、短期的な酵母細胞の拡散には小さくない影響力を持っています。またそれだけではなく、遺伝的交雑を促す機能を果たしているようなのです。
酵母の増殖は通常、クローニングやセルフリングと呼ばれる細胞分裂による方法で行われています。特にワイン用の酵母は遺伝的に見ても細胞分裂による増殖を主に行ってきた存在であることが分かっています。
しかしその一方で、酵母は有性生殖が出来ないわけではありません。一般に酵母は飢餓状態になると有性生殖の割合を増やすとされています。ショウジョウバエの摂餌行動にともなって体内に取り込まれた酵母は、極めて劣悪な生存環境におかれます。こうした環境下で酵母は十分な栄養を摂取することもできないため、生殖方法を有性生殖に切り替え、胞子を形成しはじめます。
酵母の胞子はテトラッドと呼ばれる、胞子同士が胞子間橋で連結された状態になっています。この構造体のなかでは胞子同士はお互いの距離が近いため、通常であれば非常に高い確率で近いもの同士でさらに交配するインブリーディング (inbreeding, 近親交配) が生じます。ところがショウジョウバエの腸管内では酵素の働きによってこのテトラッド構造が破壊され、それぞれの胞子同士がバラバラにされます。つまり、胞子同士の距離が物理的に遠くなることで、インブリーディングが発生しにくくなります。
この状態になった胞子はショウジョウバエの腸管内や、もしくは対外に排出された先で、それぞれが異なる親を持つ胞子同士で交雑するアウトブリーディング (outbreeding) を行う可能性が飛躍的に高くなります。
調査事例からは、ショウジョウバエの腸管内を通過することで酵母がアウトブリーディングを生じる可能性は10倍以上に増加し、1世代辺りの発生率は1.1~3.5%になると推定されています。
なお、酵母によってショウジョウバエの誘引性に差があることが分かっています。その差は平均して2.6倍ほども違っており、この誘引性の差がハエの繁殖率にも影響していることが分かっています。
誘引性の高い酵母ほどショウジョウバエに取り込まれる可能性が高くなり、その結果、距離的な拡散の機会を多く取得できるだけではなく、遺伝的多様性を獲得することにもつながっている可能性が指摘されています。
鳥を介した長距離移動
近年、鳥類が微生物の長距離媒介者であることが認知されてきています。イタリアで行われた調査の結果、鳥の腸内に取り込まれた酵母の生存可能期間はおおよそ12時間程度であることが分かりました。鳥の種類などにもよるものの、この生存時間から計算される拡散の範囲はおよそ300~350km程度と推定されています。
この調査では検体となった鳥の約33%から合計で125個の酵母細胞が検出されており、S.cerevisiaeを含む18種類の醸造関連酵母が同定されています。
越冬のための渡りを行う鳥では体脂肪率が低く、頻繁に中継地点への立ち寄りをする種類のものほど酵母の拡散に大きな役割を果たすことが確認されてもいます。
酵母の地域性とその分布
世界中で見つかっているワイン用の酵母株がそのルーツという意味では地域性をほぼ持っていないことはすでに見てきたとおりです。その一方で、それぞれに地域に到達した酵母はその地域において、様々な仲介者を媒介して遺伝的な多様性を獲得し、その変化した株がやはりベクターを介して地域的に広がっていく動きを見せています。
これまでの調査からは、そうした酵母のコミュニティはおおよそ半径100km程度の範囲ごとに形成されていることが指摘されています。この範囲内においては生息場所にかかわらずに遺伝的な均質性が高い一方で、この範囲を超えるとそうした同一性が失われていることが複数の調査を通して報告されています。
ヨーロッパから持ち込まれてきた酵母の株が、移動した先で交雑した例としてあげられるのが、北半球におけるオークの樹に棲息する酵母種との交雑です。この交雑はかなり頻繁に生じていた可能性が指摘されており、さらにワイン用株の遺伝的成り立ちにも少なくない影響を与えている可能性が示唆されています。現在分かっているワイン用菌株の遺伝的組成に対しても、かなりの割合でオーク型の遺伝子が祖先として含まれていることが分かっています。
こうした移動先の各地域における交雑を通した亜集団の形成が、いわゆるテロワールを構成する1要素としての酵母という存在を担保している可能性は高いと考えられます。
ワイン造りに、あなたらしさを活かすパートナーを
栽培や醸造で感じる日々の疑問や不安を解消し、ワインの品質をさらに高めたい──
Nagi Winesは、あなたの想いとスタイルを尊重しながら、すべての工程をともに歩みます。
経験豊富な専門家が現場に入り、知識・技術・品質の向上を、実地作業を通じて支援。
費用を抑えつつも、あなたのワインらしさを守りながら確かなフォローを行います。
まずはお気軽にご相談ください。
その酵母は本当に土地に根ざしているのか
仮に大本のルーツは同じだったとしても、S.cerevisiaeは遺伝的に変異しやすく、実際に多様性も大きいことが確認されている。しかも各地域内では鳥や昆虫を介した拡散とアウトブリーディングが行われており、地域的交雑の跡も遺伝的に確認されている。だからこそ、その土地には土地独自の酵母が存在しており、テロワールを構築するのに一役買っているのは間違いない…。そう結論してしまいたくなる気持ちはあります。しかし、まだそうだと断言することはできない、というのがおそらく公平な判断です。
ワイン造りをはじめた初期のアメリカの状況がそうであったように、酵母はヒトの手を介して世界中に広められています。またそこまで広い範囲ではなかったとしても、各地からブドウを集めてワインを醸造するという過程を通して、酵母は広範囲に移動をしています。実際の調査結果として、広い範囲からブドウを集約してワイン生産を行っている土地ほど酵母の遺伝的多様性が大きくなっていることが報告されています。それほどまでに簡単に、酵母は国や地域をまたいで移動しています。
さらにある程度以上に産地が固定化してきた現在、酵母の長距離移動を担う強力なベクターとなっているのは鳥ではなく、バリックを中心とした木樽です。
ワイナリーに納入された新樽からは、S.cerevisiaeを含む多数の、遺伝子型の異なる酵母株が検出されています。さらに、自然発酵させた果汁から検出された酵母細胞のうちもっとも数が多かったのは、未使用のバリックから検出された酵母細胞と遺伝的に一致した株でした。このことは、別の地域から持ってこられた酵母が、その地域でのテロワールを活かした発酵に強力に関わっていることを明確に示しています。
樽を媒介して持ち込まれた酵母は、さらに現地で交雑をする可能性があることも指摘されています。現在のところ、この交雑率はおおよそ30%程度と推定されています。
ワイナリー内で使用された市販酵母が近隣のブドウ畑やオークの樹に拡散していく可能性もまた、指摘されています。ある調査では、現地で採取された酵母細胞の遺伝子と商業株の遺伝子の共有率は40%以上であったことが報告されています。
酵母叢の動的平衡という考え方
多くのワイナリーでは毎年、相応の数の新樽が購入されています。つまり毎年それなりの数の酵母が地域外から新しく持ち込まれていることになります。そうした酵母がそのまま自然発酵の元になる場合もあるほか、現地での交雑をしながら拡散していく可能性があり、その結果が30%を下回る酵母の地理的依存性につながっているものと考えられます。
これは1つのワイナリーが樽を使っているとかいないとかといった話ではありません。少なくとも酵母の遺伝的同一性が100km圏内で確認されている点からは、100km以内に存在する変化の影響を誰もが等しく受ける可能性が示唆されます。また仮に、ここに鳥による媒介が関わればその範囲は300km程度まで広がっていく可能性も否定されません。酵母とテロワールの関係は、おそらく一般に考えられてきたものよりもより複雑で、動的な関係性のなかにあります。
酵母はワインの発酵に欠かすことの出来ない、もっとも重要な存在です。そしてその代謝は、ワインの味、香り、品質のすべてに多大な影響を及ぼします。ワインの特徴を語る上で、この存在を無視することはできません。
一方で、ヒトとモノの移動が活発になった現代において、この微生物をテロワールという概念の元で特定の地域に強く紐付けることはこれまで以上に難しくなってきています。これは商業的な乾燥酵母の利用を超えた、もっと根源的な移動と拡散の結果です。つまり、乾燥酵母だからテロワールの構成要素とはなり得ない、もしくは野生酵母だからテロワールの一部になり得る、そういう枠組みからは外れたところにある問題です。
これまでに見てきたとおり、土地に根ざした酵母とは、その土地固有の変化しない特性ではなく、継続的な流入と交雑による動的平衡状態によって形成されているものである可能性がもっとも高くなっています。つまり、酵母叢は常に変化しているものであり、自然発酵とはその時点でその場に存在している酵母コミュニティによって引き起こされるものである、ということです。
ワインに個性を持たせようと思うとき、そのワインが造られた土地に根拠を求めるのは現在のワイン消費においては自然な流れです。しかしそのワインの本質を担う重要な要素の1つが、実は不変の土着性を持たないものである可能性は、常に頭の片隅に置いておく必要があります。
テロワールの発想は、ワインを不変のものと結びつけることでその品質や特徴を同じく不変のものとして表現しようとする側面を持っています。一方で、最近はそうした不変と思われていた要素の多くが、変わりうるものだとして認識されつつあります。翻って、ワインの個性や品質を担保するものは、実は不変のものではなかったとみなすことが出来る環境が整いつつあります。
気候も環境も、そして酵母も。変わりうるものとして捉え直したとき、より変わりやすい存在である酵母は、どのような意味を持ち、どのような重要性を与えられるでしょうか。野生酵母とはなんなのか、そしてその価値とはなんなのか。その背景とともに、見直すべき時が来ているように思います。