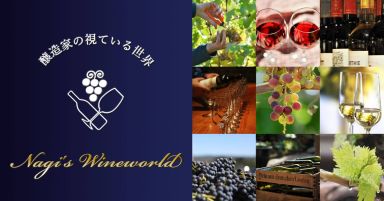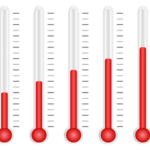ワイン、なかでも赤ワインを造るときに重要になるのが抽出という作業です。色の濃さから熟成のポテンシャルまで、すべてに抽出が関わっています。
ワイン造りにおける抽出とは、果皮や種子からそこに含まれている成分を果汁やワインの中に持ってくることを指します。赤ワイン用の黒ブドウであっても、丁寧に皮をむいて果肉だけを絞ると透明な果汁が出てきます。これを発酵させても赤い色にはなりません。ワインを赤い色に仕上げるためには、果皮に含まれる色素であるアントシアニン (Anthocyanin) を抽出する必要があります。
ワイン造りの現場では当たり前のように行われている抽出ですが、科学的根拠に基づいた条件設定などは意外なまでに行われておらず、造り手個人の感覚によっている部分も少なくありません。
この記事ではワイン造りにおける抽出というものを科学的に理解することを目指します。
ワイン造りにおける抽出の必要性
ワインを造るときに欠かせない抽出ですが、もっともその必要性が意識されるのが赤ワインの色を出すときです。赤ワイン造りで発酵を果皮と一緒に行うのも、まさにこの色素の抽出が大きな理由の1つとなります。
一方で、ワイン造りにおける抽出の意味は色素、つまりアントシアニンの抽出だけに限られるものではありません。色素は抽出の度合いが視覚的にとてもわかりやすいがために注目されやすいですが、より本質的な意味はフェノール化合物の抽出にあります。
黒ブドウの果皮に含まれている色素であり、赤ワインを赤ワインたらしめているアントシアニンもこのフェノール化合物の一種です。
フェノール化合物といってもその種類は多く、化学的な分類も少々複雑です。例えばワイン用語としてよく耳にするタンニン。これもフェノール化合物の一種であり、特にポリフェノールに分類される一部の化合物を指しています。しかもタンニンにも複数の種類があるなど、フェノール化合物を正確に理解することはあまり簡単ではありません。
それだけ多岐にわたる化学物質ですが、ワインに含まれるフェノール化合物はワインの品質を決める重要な構成要素の1つとされています。またフェノール化合物、特にポリフェノールは抗酸化作用が強くワインを酸化から守るため、ワインの熟成のポテンシャルにも影響してきます。
こうした点からも、抽出という行為がワインの色だけに対して重要なものではないのだということが分かります。
フェノールの抽出は多ければ良いのか
フェノール化合物がワインの品質に関係しているのであれば、ワインに含まれる含有量は多いほどよいものと思ってしまいがちです。そこで、そうした考えが正しい認識なのかを検証するため、フェノール化合物の含有量がとても多いワインがどうなるのかを考えてみます。
色への影響
まず外観。色が濃くなります。
アントシアニンの量が多いということはとりもなおさず色素の量が多いということ。色素の量が増えれば色は自然と濃くなります。同じアントシアニンによる着色で分かりやすいのがブルーベリージュースやジャムです。含まれているアントシアニンの種類や処理方法の違いによる部分もありますが、ブルーベリーはアントシアニンの含有量が多いため、あのような色の濃いジュースやジャムになっています。
味への影響
次に味です。収斂感が強くなり、苦みも出てきます。
赤ワインの中には口に含んだ時に強い収斂感を感じるものがあります。あの渋みはタンニンによるもので、タンニンの含有量が増えると収斂感も強くなっていきます。含有されるタンニンの量が極端に多くなった場合の例が、渋柿です。渋柿に含まれるタンニンの含有量は赤ワインに含まれるものよりもはるかに多いため、ワインがあそこまで渋くなることはありませんが、仮に際限なくフェノール化合物の抽出量を増やしていける場合にはああした収斂感に近づいていくことになります。
またタンニンなどが分類されているFlavonoid類は苦みの原因物質でもあることがこれまでの研究で示されています。このため、フェノール化合物の含有量が増えるとそれに伴って苦みも強くなっていく可能性があります。
フェノール類を多く含んだワインは色が濃く、抗酸化力も強い長期熟成に耐えるワインになる可能性が高くなる一方で、強い収斂感と苦みを伴うものになります。バランス次第ではあるものの、フェノール化合物の量だけが突出して多い場合にはあまり美味しいワインにはなりません。つまり、ワインにおいてフェノール化合物は多ければ多いほど良い、という類のものではないのです。
醸造における抽出量管理の難しさ
仮にワインに含まれるフェノール化合物が多すぎたら何が起きるのかを見てきました。これは醸造的に言い換えれば、とても多くのフェノール化合物を抽出したらどうなるのか、という意味に他なりません。そして同時に、現実味の薄い仮定でもあります。
ワインの醸造においていくら抽出を多くしようと頑張ってみても、ワインが渋すぎて飲めなくなるほど多量のフェノール化合物を抽出できることはほぼありません。抽出量の管理は実はとても難しい作業なのです。
上げたくても上がらない抽出率
そもそも抽出という行為は、抽出を行う対象、ワイン造りの場合は原料となるブドウに蓄積されている量がその対象物質を抽出できる物理的な上限となります。フェノール化合物の蓄積量はブドウ品種によって差があり、比較的多くの含有量を持つ品種もあれば、そもそも蓄積量が少ないブドウ品種もあります。また栽培条件による影響も大きく、同一品種であったとしても蓄積量に差が出ることは珍しくありません。もともとの蓄積量が少ない品種を使っている場合、どれだけ醸造的に頑張ろうと抽出できるフェノール化合物の量には限りがあります。
さらに重要な点として、ブドウに含まれているフェノール化合物の全量を抽出することはできないことが複数の検証を通して分かっています。ワイン造りにおけるフェノール化合物の抽出率はどれだけ条件を振ってみてもそれほど高くならないのです。
抽出率の目安
醸造期間中における抽出率はブドウへの蓄積量に加え、エタノール濃度や温度、液固比、pHなど多くの要素が複雑に関係しています。唯一条件に支配されない複雑系の反応であるため、これまでに絶対的な抽出率の平均値は提示されていません。また検証を通して得られた結果にも一貫性は見られていません。
例えばアントシアニンは一部で80%の抽出率を出したとする検証事例がある一方で、45%程度に留まると報告している例も多くあります。タンニンもおおよそ同様の傾向が報告されています。基本的なフェノール化合物の抽出傾向はアントシアニンのそれと大きく変わらないという指摘がなされていることを考えると、あくまでも個人的な予想の範囲となりますが、抽出率としては40~60%程度に留まる傾向が強いと考えておくのが妥当のように思います。
抽出を促すための4つの条件
ワイン醸造における抽出は複数の要因が関係した複雑系の反応として捉えられます。過去に行われてきた複数の検証結果にも一貫性はみられません。しかしその一方で、そうした中でも特に影響力が大きいと判断できる、重要な要素が4つあります。それが、温度、接触時間、エタノール濃度、そして果皮や種子の硬度です。
温度と硬さと抽出の関係を知る
一般に温度が高い方が抽出の効率が高くなる傾向が示されています。赤ワインの醸造手法に高温抽出法と呼ばれる、発酵前に果汁を70度程度で処理する手法が存在するのはこのためです。
また温度を用いた処理は果皮や種子の硬度とも密接に関わっています。
例えば色素であるアントシアニンはブドウの果皮を構成する細胞壁中に含まれています。このアントシアニンをより効率よく抽出するためには、なんらかの方法で果皮の細胞構造を壊すか、構造を緩めるかすることが重要な意味を持ちます。抽出効率はこの構造が柔らかくなるほど高くなる傾向が示されています。
果皮を軟化させる要素は複数あり、温度や酵素、エタノール濃度などが関係しています。そうしたなかでも温度はそれ自体の影響に加え、酵素の働きを活発化させるなど間接的な影響も及ぼす重要な要素となっています。
また温度は上げる場合だけではなく、下げる場合でも抽出に影響を与えます。その代表例がクリオエクストラクションです。クリオエクストラクションは収穫したブドウを人工的に凍結させる醸造手法で、文字通り抽出率を上げることを目的の1つとして行われます。この処理を行うことで抽出効率が高くなるのも、細胞構造を破壊して果皮硬度を下げることで抽出しやすくなるためです。
いつ、何が出てきているのかを理解する
抽出といってしまうとすべてが同じ効果をもたらすもののように感じてしまいます。しかし実際にはもっと動的なものとして、一定の時間軸の中で生じる連続した変化として捉える必要があります。
フェノール化合物というカテゴリーには多数の異なる種類の化合物が含まれています。またそれぞれの特徴も驚くほどに違います。そうした違いのなかでも特に分かりやすい差が、溶解性の違いです。
抽出という行為は果皮や種子から固形の粒としてフェノール化合物を取り出してくるものではありません。果皮や種子の中に存在するフェノール化合物が周囲の液体に溶け出してくることで生じる現象です。
フェノール化合物のなかにはより水に対して溶けやすいものもあれば、アルコールに対して溶けやすいものも存在します。ワイン醸造の流れの中で、最初の時点ではアルコールはまだつくられていないため液体中の水とアルコールの比率は100:0です。一方で酵母によるアルコール発酵が進んでいくと徐々にアルコールの濃度が高くなっていきます。
これは、フェノール化合物のなかでも水に溶けやすいものは比較的最初のうちから溶け出してくる一方で、アルコールにしか溶けないようなものは発酵の後半にならないと抽出されないということでもあります。抽出をコントロールするためには、自身が抽出したいものがどの時点でどれくらい抽出される性質を持っているのかを知っておく必要があるということです。
浸漬期間は長ければ長い方がいいという誤解
果皮や種子からより多くのフェノール化合物を抽出するためにはより長い期間、果皮や種子を果汁やワインと接触させておくのがいいという考えがあります。そうした考えのもとでは、発酵前に数日、発酵が終わってからもまた数日、果皮や種子を果汁やワインに浸漬したままの状態にしておきます。
エクステンドマセレーション、もしくは延長マセラシオンと呼ばれる醸造手法があります。これは発酵が終了した後もすぐにはプレスして果皮とワインを分離せずにそのまま浸漬させ、より多くのものを抽出しようとする醸造技術です。
この技術を使うことで種子に存在するタンニンなど、エタノール濃度が高い環境下でより多く抽出される傾向をもったフェノール化合物のワイン中での含有量を増やせることが分かっています。しかしその一方で、アントシアニンなどの含有量は減少する傾向が示されています。減少量はある報告によると44~82%にものぼったとされています。
こうした減少量はエクステンドマセレーションにより得られる量を多くの場合で上回っており、長期の抽出はかえってワイン中の総フェノール含有量を低下させることになることが多くの研究を通して示唆されています。抽出しようとするフェノール化合物の種類にもよりますが、少なくとも抽出期間を長くすればそれだけ多くのものが抽出できると単純に考えるのは明確な誤りです。
ワイン中のフェノール含有量を規定する平衡状態という考え方
そもそもブドウに含まれていないフェノールは抽出できない一方で、仮にブドウには多量のフェノール化合物が蓄積されていたとしても、そのすべてがワインに抽出できるわけではないことがフェノール化合物の抽出を考える上でとても重要な点となります。フェノール化合物は果汁やワイン中にいくらでも溶け込むことができるわけではなく、その量には上限が存在しています。
また同時に、一度果汁やワインに抽出されたフェノール化合物はそのまま安定して維持されるわけではありません。反応や沈殿、吸着といった要因を通して減少する可能性があり、その含有量は常に変化していると考えられます。
抽出はワインが保持できるだけの量までしか行うことができませんが、一度上限に達したらそれで終わりというわけではありません。例えば発酵中に酸化による沈殿で損失が生じた場合、その損失分が追加で抽出され供給されるというバランスの取り合いが常に行われています。
この供給と損失が常に繰り返されながらも両者のバランスがとれている状態を動的平衡状態といいます。そして、抽出によってワイン中に取り出すことのできるフェノール化合物の最大量は、この平衡状態によって規定されていると考えられています。つまりこのバランスを超えた量の抽出はできないということです。
仮に一時的にこのバランスを崩して多量のフェノール化合物を抽出したとしても、そうした状態は短期間しか維持できないことがすでに検証を通して確認されています。過剰抽出物の保持期間は短い場合で数週間から数ヶ月、長くても数年程度とされています。複数の検証事例からはそうした期間を通して含有量が徐々に低下し、最終的には通常の抽出を行ったものと同等か、場合によってはより少ない含有量に落ち着いたことが報告されています。
ワイン造りに、あなたらしさを活かすパートナーを
栽培や醸造で感じる日々の疑問や不安を解消し、ワインの品質をさらに高めたい──
Nagi Winesは、あなたの想いとスタイルを尊重しながら、すべての工程をともに歩みます。
経験豊富な専門家が現場に入り、知識・技術・品質の向上を、実地作業を通じて支援。
費用を抑えつつも、あなたのワインらしさを守りながら確かなフォローを行います。
まずはお気軽にご相談ください。
今回のまとめ|抽出だけ増やしても意味はない
ワイン醸造において抽出を考えるとき、多くの場合はどうやって抽出量を増やすのかにばかり意識を向けてしまいがちです。しかしこうした視点からは、残念なことに良好な結果を得られることはあまり多くはありません。
すでに見てきたとおり、抽出は取り出すことだけを考えても片手落ちになってしまう化学的な現象です。いくら抽出してみても維持できる上限が平衡状態によって規定されているのであれば、結局は維持することができずに失われてしまい意味がないからです。抽出はワイン中により多くの対象物質を取り込むために行う行為です。これはつまり、本質的に重要なのは取り出す量ではなく、取り出した後に維持される量であるということです。
では取り出したものをより多く維持し、結果的に抽出の効率を上げていくためにはどうすれば良いのでしょうか。それはワイン中で損失につながらずに維持されるフェノール化合物の量を増やすことを考える必要があるということであり、平衡点を形成する条件を変えていくことを考える必要があるということです。
現時点において平衡点を変化させる要素として分かっている対象は、温度や酸化還元状態、エタノール濃度、そして多糖類含有量などです。これらの要素を調整することで平衡点の位置を動かし、新たな平衡状態を形成することができます。しかしその一方で、平衡点の固定的な最適値が存在しないことも指摘されています。つまり、どのような調整をするべきなのかに対する絶対的な正解は存在しません。
そうした中でより効率的で効果的な抽出を行うためには、抽出期間だけではなくその後の管理期間まで含めた視点が必要です。醸造プロセス全体を通しての抽出設計を作り、それぞれの時点で最適な対応を積み上げていくことが欠かせません。