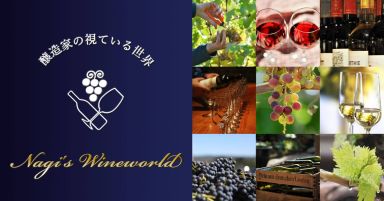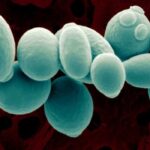ワインを学んでいてVAという表現に出会ったことがあると思います。このVA、最初はなんのことを言っているのか分からなかった方も少なくないのではないでしょうか。
VAとはVolatile Acidの略で、日本語では揮発酸と訳されます。揮発酸は正しくは揮発性酸といい、常温常圧で揮発する性質を持った酸のことです。
ワインには酒石酸やリンゴ酸など、多くの酸が含まれています。これらの酸のうち、常温常圧下では揮発しないものを不揮発性酸と呼びます。ワインに含まれる酸のうち、揮発性のものは実はほとんどなく、大部分は不揮発性の酸で構成されています。そのなかの例外が酢酸です。そのため、ワインに限れば揮発酸はほぼ酢酸と同じ意味で使われています。VAの測定値も、基本的には酢酸量として記載されます。
酢酸といえばお酢のことです。料理などで使用するお酢を想像してみれば分かりますが、高濃度の酢酸はとても強い臭いと刺激を伴った味をしています。そうした影響はワインにおいても同様で、一定以上の強さを持った酢酸系の香りは欠陥臭、オフフレーバーとして扱われます。高濃度の揮発酸は腐敗度の指標とみなされているのです。
そうした揮発酸ですが、ワインのオフフレーバーとしてはかなり発生頻度の高い部類に入ります。同じく発生頻度の高いオフフレーバーとしては還元臭がありますが、ワイン造りの面からみると揮発酸によるものの方がより危険度の高い欠陥臭といえます。
なぜ揮発酸によるオフフレーバーがそれほど頻繁に発生するのか、またなぜ醸造的な危険度が高いのか、その理由を解説していきます。
ワインに含まれる揮発酸
ほぼすべてのワインには多かれ少なかれ揮発酸が含まれています。これはワインの製造工程上、酢酸の発生を避けることができないためです。
一方でワインに含まれてもいい揮発酸の量は多くの国や地域において法的に定められています。
一般に辛口のワインに含まれる量は0.2~0.6g/Lとされていますが、甘口のワインなどでは含有量が多くなります。OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin: 国際ブドウ・ワイン機構) による規定では、通常のスティルワインの場合には酢酸換算で1.2g/L、貴腐ワインなどの極甘口ワインでは2.1g/Lが含有量の上限とされています。
こうした規定値は基本的にワインをボトリングする時点で測定した数値で管理されます。ワイン中における揮発酸の含有量は熟成など、保管期間中に生じる変化を通して増加する場合があります。このため、長期熟成したワインからは規定値以上の揮発酸が検出される可能性があります。
揮発酸の味や臭いを感じるかどうかの境界線となる官能閾値はブドウの品種やワインのスタイルによって変動することが知られています。一般的には0.5g/L程度の濃度から感知できるようになると言われている一方で、0.9g/Lの含有量があっても必ずしも味や香りとして認識できない場合があることも検証を通して確認されています。
揮発酸がワインに含まれる3つの理由
ワインを造っていくうえで揮発酸が含まれるのはその量の多寡を別にすれば不思議なことではなく、むしろ当然ともいえます。そうした意味で、揮発酸はワインにおける必須の含有成分とみることもできます。
ワイン中に揮発酸が含まれるようになる理由は大きく分けて3つあります。醸造に活用される微生物による酢酸の生成、腐敗果による持ち込み、そして管理上の不備です。それぞれを詳しく見ていきます。
醸造用微生物と酢酸の関係
ワイン造りには複数の微生物の関与が欠かせません。そうしたなかでも大きな役割を果たしているのが、酵母と乳酸菌です。
酵母によるアルコール発酵中の酢酸生産
酵母はブドウ果汁をアルコール発酵させ、ワインに変える重要な役割を担います。
ワイン造りでは主にSaccharomyces cerevisiae (サッカロミセス セレビシエ)という種類の酵母が使われます。この酵母はパンや日本酒、ビールなど、ほぼあらゆる発酵食品に関わっているだけでなく、食品以外の分野でも活用されるなど、私たちの生活に深く根付いています。とても重要な存在であるこのS.cerevisiaeが、糖を代謝していく過程で酢酸を作ります。これはつまり、S.cerevisiaeが発酵に関わっている製品ではそのほぼすべてのものに揮発酸が含まれているということでもあります。
S.cerevisiaeが作り出す酢酸の量は菌株の種類や発酵の環境や条件によって大きく異なります。ワイン造りの環境では、ほとんどのケースで0.2~0.4g/Lの範囲に収まるといわれています。ただし酵母による酢酸の生産は果汁中に含まれる糖濃度に比例するため、含有糖量の多い果汁を発酵させる場合には生産される酢酸量も増えていくことになります。
なお世の中にはS.cerevisiae以外にも様々な種類の酵母が存在しています。そうした酵母の中には1g/L以上という多量の酢酸を生産するものも確認されています。
MLFが増やす揮発酸含有量
一般的なワイン造りをしていく上で使用する可能性の高いもう1つの微生物が、乳酸菌です。
乳酸菌はワインに含まれるリンゴ酸をより酸度の低い乳酸に変換することを目的に使用されています。これをMLF (Malolactic fermentation: マロラクティック発酵)や乳酸発酵と呼んでいます。
乳酸菌にはホモ型とヘテロ型と呼ばれる2つの種類の菌が存在しています。ワイン醸造で主に利用されているOenococcus oeniという乳酸菌はヘテロ型に分類される菌株です。このヘテロ型の乳酸菌が代謝の過程で酢酸を産生することが知られています。
乳酸菌による酢酸の生産量も酵母と同様、環境による影響を大きく受けるものの、0.4g/L程度から多い場合には1g/Lを超える量の酢酸を生産するとされています。またMLFを行う上での技術の1つ、コ・イノキュレーション (Co-inoculation) は乳酸菌株による酢酸の生産量を増やす可能性があるとの指摘もされています。
腐敗による酢酸含有量の増加
酵母や乳酸菌による酢酸の生産は無視していいものではありません。しかしワインを造っていく上で避けようのない部分もあり、仕方のないものとして受け入れざるを得ないところがあります。それに対して、絶対に避けなければならないのが腐敗果を原因とする酢酸含有量の増加です。
冒頭で高濃度の酢酸含有は腐敗度の指標であると書いたとおり、酢酸の含有量はブドウの健全性と強い関わりがあります。ここに関係しているのが、酢酸菌です。
酢酸菌の種類とワインへの影響
酢酸菌とは酵母や乳酸菌と同じ微生物の一種です。名前の通り酢酸の生産能力がとても強い細菌で、お酢の製造に欠かせない微生物でもあります。ヒトの生活全般で見れば有用性の高い微生物なのですが、ワイン造りの現場では一貫して悪者として扱われています。
乳酸菌はホモ型とヘテロ型の2種類に大別されますが、酢酸菌はさらに多くの種類に分類される、非常に種類の多い細菌群です。そうしたなかでワイン造りの現場に特に関係が深いのが、グルコノバクター属 (Gluconobacter) とアセトバクター属 (Acetobacter) という2つの属に分類される酢酸菌です。
どちらの酢酸菌も自然界に普通に存在しているものですが、健全なブドウの果皮上には主にグルコノバクター属の酢酸菌が棲息しています。一方で腐敗したブドウの果皮上ではアセトバクター属の酢酸菌が多くなります。この理由はそれぞれの菌株が消費するエネルギー源にあります。
グルコノバクターに属する酢酸菌は主にグルコースを代謝します。一方でアセトバクターに属する酢酸菌はエタノールを代謝します。同じ酢酸菌ですが、生態が全く異なるのです。
ちなみにグルコノバクター属の菌株は酢酸に対する耐性が低く、低濃度の酢酸で生育が阻害されるため酢酸生産効率が悪い株です。これに対してアセトバクター属の菌株は高い酢酸耐性を持っており、効率的に酢酸を産生することができます。これらの違いから、アセトバクター属の酢酸菌の方がワインに対してより大きな影響を及ぼします。
ボトリティスと野生酵母と酢酸菌の深い関係
酢酸菌が増殖しやすいブドウの1つにボトリティス シネレア (Botrytis cinerea:以下、Botrytis) というカビに罹患したブドウが挙げられます。Botrytisは貴腐菌として知られ、このカビが付着したブドウは貴腐ワインの原料となる貴腐ブドウとなります。一方でBotrytisに感染したブドウの房は多くの場合、同時に相当数の腐敗果を含んでいます。こうした腐敗果を生む原因の1つが、アセトバクター属の酢酸菌です。
Botrytisはブドウの果皮表面に付着すると、そこから菌糸を伸ばしてブドウの果皮に穴を開けます。この穴からは果汁が漏れ出してくるだけではなく、細菌類がこの穴を通って直接ブドウの果肉や果汁に接触することができるようになります。ここで動き出すのが野生酵母です。
野生酵母はもともとブドウの果皮表面にも付着しています。そうした酵母がBotrytisによって漏れ出した果汁や、開いた穴に入って直接果汁に触れることで糖分を取り込み代謝をはじめます。これにより、微量とはいえエタノールが作り出されます。
もともとブドウの果皮表面にいたグルコノバクター属の酢酸菌は漏れ出てきた果汁を餌にはしても、野生酵母によって作り出されたエタノールは消費しません。一方で、これを消費するのがアセトバクター属の酢酸菌です。
野生酵母が積極的に作り出すエタノールをエネルギー源にアセトバクター属の酢酸菌はその数を爆発的に増やしていきます。通常の健全果にはおよそ10²~10⁴ 細胞/ml程度しか存在しなかった酢酸菌が、ブドウのBotrytis感染後には最大で10⁷ 細胞/mlという膨大な量に達したことが確認されています。
酢酸菌が大増殖したブドウにはその細胞数に応じて多くの酢酸が含まれます。腐敗したブドウでツンとした酸っぱい臭いがするのもこうして生産された酢酸が原因です。
腐敗したブドウを収穫物として醸造所内に持ち込むことの一番の問題は、すでに生産された酢酸を持ち込んでしまうことよりも、その原因となっている大量の酢酸菌を生きたまま持ち込むことにあります。
すでに見てきたように、アセトバクター属の酢酸菌はエタノールを消費して酢酸を作り出します。酢酸菌がやっかいなのは、この微生物がS.cerevisiaeによるアルコール発酵中にも死ぬことがなく、発酵が終わるまで生存することができる点です。つまり、一度醸造所内に持ち込まれた酢酸菌は、もともとブドウの表面で作っていた酢酸に加えて、醸造所搬入後に酵母が作り出したエタノールを使ってさらに酢酸を生産することができるのです。
なお、こうした状況はなにもBotrytisに罹患したブドウに限った話ではありません。昆虫による食害や降雨によって果皮が損傷したブドウであっても、同様のことが起こりえます。
管理の不備がワインを酸っぱくする
最近はあまり聞かなくなりましたが、ワインを置いておくとお酢になる、という話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。実際のところ、ボトリングされたワインを保管しておいて完全なお酢になることはまずありません。一方で、味が酸っぱくなる可能性はゼロではありません。
こうした味の変化は主に前述の酢酸菌の働きによるものです。酢酸菌が働くならお酢になるのでは、と思われるかもしれません。しかし、酢酸菌がもっとも活発に動く環境と一般的にワインが保管される環境とでは条件に大きな差があるため、ワインが完全にお酢になるほど酢酸菌が動くことはまずありません。
そうした酢酸菌がより動くための条件の1つが、酸素の供給があること、です。
酢酸菌は好気性菌と呼ばれる、活動のために酸素を必要とするタイプの細菌です。通常、ワインの発酵中は発酵ガスとして二酸化炭素が酵母から常に排出されています。この作用により発酵槽内は嫌気的環境、つまり酸素がほとんどない状態に保たれています。こうした環境では酢酸菌は生存することはできても活発に活動することはできず、酢酸菌による酢酸の産生はほとんど行われません。
また出来上がったワインをボトリングする際には、多くの場合は事前に濾過をしてワイン中の微生物類を除去します。この作業によって酢酸菌も除去され、ボトル内に残る可能性はそれほど高くはなくなります。危険なのは、この間の期間です。
アルコール発酵を終えたワインは瓶詰めされるまでに一定の期間、タンクなどの容器の中で保管されることがあります。バリックと呼ばれる木樽を使った熟成などはまさにこの代表的な例です。この期間中、ワインは発酵ガスに守られることもなく酢酸菌をはじめとした各種微生物に晒されることになります。
熟成期間中、ワインを入れている容器は常に満量で維持されなければならないとされています。こうすることの理由はワインの酸化と結びつけて説明されることが多いですが、同時に酢酸菌のような好気性細菌の活動を抑制する上でも満量管理はとても重要な意味を持っています。
ワインが原料となるブドウを仕込み前に洗浄していないにもかかわらず衛生的な飲み物として認知されている理由に、ワインが低いpHや比較的高めのアルコール度数で守られていて一般微生物が生存するには困難な環境であることが挙げられます。一方で酢酸菌はこうした過酷な環境でも生存できる例外的な微生物です。そんな酢酸菌は収穫されたブドウの状態によっては大量に醸造所内に持ち込まれる可能性があります。そうした環境の中で、ワインの満量管理を怠ってしまえば、潜伏していた酢酸菌が一気に動き出す可能性はとても高くなります。
酢酸はブドウの腐敗度を示す指標であるのと同時に、ワインの管理度合いを示す指標にもなり得ます。
ワイン造りに、あなたらしさを活かすパートナーを
栽培や醸造で感じる日々の疑問や不安を解消し、ワインの品質をさらに高めたい──
Nagi Winesは、あなたの想いとスタイルを尊重しながら、すべての工程をともに歩みます。
経験豊富な専門家が現場に入り、知識・技術・品質の向上を、実地作業を通じて支援。
費用を抑えつつも、あなたのワインらしさを守りながら確かなフォローを行います。
まずはお気軽にご相談ください。
今回のまとめ|ワインの揮発酸をコントロールするには原因を切り分けた対処が不可欠
ワインに揮発酸が含まれるようになる原因は複数ありますが、それらを扱ううえで重要なのは、影響をゼロにできるものとできないものがあることをまずは明確に認識することです。影響をゼロにできるものとは、発酵に関わらない要因です。これに対して、影響をゼロにはできないものが発酵に直接関わっている要因です。
すでに見てきたように、例えばアルコール発酵を行う酵母は発酵の過程で酢酸を産生します。酵母の種類や発酵条件を調整することで産生量は減らせますが、完全になくすことはできません。MLFを行う場合には、乳酸菌に関しても同じことがいえます。
一方で酢酸菌をはじめとしたいわゆる雑菌類による酢酸の産生は、努力次第で避けることができます。そのためにはブドウ畑での作業や収穫したブドウの選果などの前処理、醸造所の清掃度や管理水準の引き上げといった各種作業が求められますが、不可能な取り組みではありません。
ワイン中に含まれる揮発酸量をコントロールするには、まずは自分自身で管理できる部分をしっかり押さえた上で、管理の難しい部分を可能な限りコントロールしようとするのが効果的です。
揮発酸はその他のオフフレーバーと同様に、一度ワインに含まれてしまうと完全に除去することは極めて難しいものです。ある一定の割合までは仮に含まれていたとしても認識できないとはいえ、その水準まで量を減らすことも簡単ではありません。
一方で揮発酸は含有濃度が上がれば欠陥臭になってはしまうものの、その特徴的な味や香りから、ワインの構成成分としてはなければない方がいい、というものでもありません。完全に排除することを目指すのではなく、適切な濃度をどう維持するのかが、この化合物との正しい向き合い方になると言えます。
そのような調整を行っていくためには、ワインに含有されてしまった揮発酸をどうすれば減らすことができるのかも知っておく必要があります。またそうした方法を知ることは、揮発酸を増やさない発酵を行っていく上での参考にもなります。
一度含有されてしまった揮発酸の濃度を再調整するための手法については、別の記事で解説をしていきます。