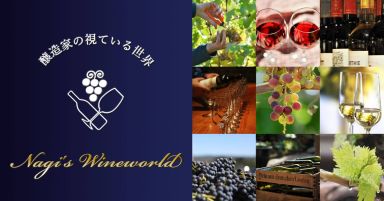現代のワイン醸造において、技術の選択には絶えず変化が見られます。その中でも特に顕著な変遷を示すのが酵母の選択です。品評会での好成績や業界での推奨により、特定の酵母が注目を集め、次のヴィンテージではその採用が急速に拡大するという現象が繰り返されています。
醸造用酵母の選択肢は多岐にわたり、カタログに掲載されているすべての酵母を網羅的に検証することは現実的ではありません。さらに、野生酵母による自然発酵という選択肢も加わることで、使用される酵母株の多様性は年々拡大し続けています。このような状況において、造り手が最適な酵母を選択することの困難さは想像に難くありません。
こうした酵母選択の多様化が進む中、近年特に注目を集めているのが非サッカロミセス系酵母 (non Saccharomyces wine yeast) です。この酵母群は、従来の醸造技術では得られなかった自然発酵特有の特徴を、より安全で制御された環境下で実現できる可能性を秘めているとして高く評価されています。
本稿では、非サッカロミセス系酵母とは何なのかを焦点に、より基礎的な理解を深めることを目的としています。
非サッカロミセス系酵母と野生酵母の関係性
非サッカロミセス系酵母について論じる際、最も頻繁に寄せられる質問の一つが、「非サッカロミセス系酵母とは野生酵母のことなのか」という点です。確かに、この酵母系統の説明において「自然発酵に近い効果を得られる」という表現が多用されることから、このような疑問が生じるのは自然な流れといえるでしょう。
結論から申し上げますと、非サッカロミセス系酵母と野生酵母は同義ではありません。より正確に表現するならば、野生酵母のすべてが非サッカロミセス系酵母に分類されるわけではない、ということになります。
野生酵母の本質的定義
野生酵母、または天然酵母という用語は、主として市場に流通している商業的な乾燥酵母製品に対する対比概念として使用されています。その定義は「自然界に存在する酵母」という極めて広義なものであり、それ以上の具体的な分類学的特徴を内包するものではありません。
従来、ワイン醸造用酵母の主流はサッカロミセス・セレビシエ (Saccharomyces cerevisiae) という単一の酵母種が占めていました。市場に流通する乾燥酵母製品の大部分がこの系統に属していたため、「乾燥酵母=サッカロミセス系酵母」という等式が成立していました。この状況から、「乾燥酵母ではない酵母=非サッカロミセス系酵母=野生酵母」という誤った連想が生まれたと考えられます。
しかし、この認識は根本的な誤解に基づいています。野生酵母とは単に「乾燥酵母製品として加工されていない酵母」を指すものであり、必ずしもサッカロミセス系以外の酵母であることを意味するものではありません。
商業的な乾燥酵母製品もまた、その起源を辿れば自然界由来の菌株です。これらの酵母は、自然界から分離された菌株を交配や選別によって改良したものか、あるいは自然界から採取されたままの状態で製品化されたものです。いずれの場合も、その出発点は自然界に存在していた野生酵母、すなわち天然酵母なのです。
従って、野生酵母という概念の中には、サッカロミセス系酵母も非サッカロミセス系酵母も等しく含まれています。野生酵母と非サッカロミセス系酵母を同一視することは、科学的に正確ではありません。
自然発酵との相違点
非サッカロミセス系酵母の利用と自然発酵による醸造は、表面的には類似しているように見えますが、実際には明確に異なる醸造手法です。
自然発酵においては、確かに非サッカロミセス系酵母が関与する可能性は高いといえます。しかし同時に、この発酵形態では関与する酵母の種類や優勢度を予測することは不可能です。自然発酵において、非サッカロミセス系酵母が全く関与しない可能性も、低い確率ながら存在します。
興味深いことに、ブドウ果皮上に存在するサッカロミセス系酵母の割合は、多くの研究において全体の数パーセント程度とされています。この数値だけを見ると、自然発酵では非サッカロミセス系酵母が主導的な役割を果たすと予想されるかもしれません。
しかし、微生物間の競争は予想以上に複雑で動的な現象です。発酵開始時に圧倒的多数を占めていた非サッカロミセス系酵母が、短期間のうちに死滅し、少数派であったサッカロミセス系酵母が発酵プロセス全体を支配するという事例も数多く報告されています。自然発酵における微生物相の変遷は、極めて流動的で予測困難な現象なのです。
これに対して、非サッカロミセス系酵母を意図的に使用する醸造手法は、このような不確実性を可能な限り排除し、特定の酵母による発酵を確実に実現することを目的としています。これは、自然発酵が持つ偶然性を制御された環境下で再現しようとする試みといえるでしょう。
ただし、このような制御された発酵を実現するためには、使用する酵母の系統に関わらず、適切な環境整備と技術的な管理が不可欠です。これらの人為的な操作は、自然発酵の理念とは相反する側面を持ちます。特に、特定の非サッカロミセス系酵母に期待される役割を確実に果たさせるためには、より高度な技術的介入が必要となります。
非サッカロミセス系酵母への注目が高まる背景
非サッカロミセス系酵母を醸造プロセスに組み込むという概念は、研究分野では20年近い歴史を持ちます。実際の醸造現場においても、数年前から採用する生産者が着実に増加しています。技術革新としては必ずしも最新のものではありませんが、その普及には段階的な発展が見られます。
初期の段階では、サッカロミセス系酵母と非サッカロミセス系酵母の交配株や、両系統の酵母による混合培養製品が商品化されていました。その後、予め両系統の酵母を配合した製品も市場に登場しました。そして近年、非サッカロミセス系酵母のみで構成された製品が本格的に上市されるようになり、この技術の採用者が大幅に拡大したのです。
現在では、酵母製品の開発が活発化しており、非サッカロミセス系酵母100%の製品をカタログ上で見つけることは容易になっています。この市場拡大において、Laffort社のAlphaをはじめとする製品が果たした役割は特筆すべきものがあります。
ワインの差別化に対する需要の高まり
従来、非サッカロミセス系酵母の多くは腐敗酵母として一括して扱われてきました。これらの酵母がサッカロミセス系酵母では産生されない独特の香りや特徴をワインに付与することは知られていましたが、それらの特徴は主にワインの品質に悪影響を与えるものとして忌避されてきたのです。
実際、多くの非サッカロミセス系酵母株は酢酸系の香気成分を産生することが確認されており、現在のように積極的な利用が検討されている状況においても、その取り扱いには細心の注意が求められます。
しかし、ワインの特徴を差別化する手段として、これらの酵母への関心は着実に高まっています。この背景には、ワイン醸造技術の世界的な標準化があります。
現代のワイン産業において、醸造設備や環境管理技術は国際的な規模で標準化が進んでいます。世界中の生産者が同様のステンレスタンクや木樽を使用し、同一の温度管理システムを導入し、同じ酵母製品を選択できる時代です。原料となるブドウの特性に差異があったとしても、醸造プロセスの根本的な部分では同質性が避けられない状況が生まれています。
このような状況において、ワインに独自性を付与するための手段として、従来使用されることの少なかった非サッカロミセス系酵母が注目されているのです。
前述したように、非サッカロミセス系酵母が商業製品として市場に供給されるようになったことも、この動向を加速させています。未知の腐敗酵母を使用することには相当なリスクが伴いますが、詳細な使用説明書が付属した製品であれば、そのリスクは大幅に軽減されます。加えて、製品化されていることによる心理的な安心感も、採用を促進する要因となっています。
新規性への需要が高まる中で、その実現手段の使用難易度が低下したことが、現在の人気を支える重要な要素となっています。
ワイン醸造における非サッカロミセス系酵母の実際的な応用
非サッカロミセス系酵母を用いたワイン醸造は、概念的には単純に聞こえるかもしれませんが、実際の応用は相当な複雑性を伴います。
現在の酵母製品カタログには膨大な数の商品が掲載されていますが、その大部分、おそらく8割から9割はサッカロミセス系酵母です。これは、サッカロミセス系酵母と分類される酵母に、それだけ多様な株が存在することを意味しています。
重要なのは、このサッカロミセス系酵母が、酵母全体の中では単一の系統に過ぎないということです。残りのすべての酵母は非サッカロミセス系に分類されます。つまり、自然界には想像を超える数の非サッカロミセス系酵母が存在しているのです。
しかし、この膨大な数の非サッカロミセス系酵母の中で、ワイン醸造に適した特性を持つものは限られています。従来から指摘されているように、ワインに対して有害な影響のみを与える完全な腐敗酵母も多数存在しており、非サッカロミセス系であれば何でも良いということではありません。
醸造において非サッカロミセス系酵母を使用するということは、ワインに悪影響を与えない特性を持ち、かつサッカロミセス系に属さない酵母株を選択して使用することを意味します。この選択には、高度な専門知識と慎重な判断が求められます。
さらに重要な点として、多くの場合、非サッカロミセス系酵母単独でアルコール発酵を完全に終了させることは困難であるということが挙げられます。アルコール耐性の制約や発酵速度の問題により、サッカロミセス系酵母との併用が一般的に推奨されています。これは、単独使用時に発生する可能性のある発酵トラブルを回避し、確実な発酵完了を保証するための重要な措置です。
この併用システムでは、発酵初期に非サッカロミセス系酵母が活動し、ワインに独特の特徴を付与した後、サッカロミセス系酵母が引き継いで発酵を完了させるという段階的なプロセスが採用されます。このプロセスの管理方法によっては、発酵が上手くいかないといった問題が発生したり、期待した味や香りが得られないといった結果につながったりすることがあります。
品質安定性を重視する生産者のための新たな選択肢
ブドウ果汁の発酵において、人為的な介入を最小限に抑えて自然に委ねるアプローチは、ある意味で不確実性を受け入れる姿勢といえます。人的介入を行えば、結果は概ね予測可能な範囲に収まりますが、介入を控えることで、予想を超える優れた結果が得られる可能性が生まれます。この期待感が自然発酵の魅力の一つです。
しかし、このような偶然性への期待には、商品として成立しない品質のワインが生産されるリスクが必然的に伴います。特に酵母に関していえば、ワインに良い影響を与える存在はごく限られており、大部分は無影響か、あるいは悪影響を与える存在です。確率論的に考えると、自然発酵による恩恵を受けられる可能性は決して高くありません。
このため、製品品質の安定性を最優先とする生産者にとって、自然発酵は採用しにくい選択肢となります。そのメリットを理解していても、無視できないリスクが決断を妨げるのです。
商業化された非サッカロミセス系酵母製品は、このような躊躇を軽減する解決策を提供します。予測不可能性による不安を減少させながら、自然発酵で得られるような複雑性をワインに付与する可能性を提供するのです。正体不明の雑多な酵母群ではなく、特性と効果が明確に把握された純粋な非サッカロミセス系酵母であることが保証されています。これらの特性は、安定した醸造を志向する生産者が長らく求めてきたものです。
ただし、ここでいう「安定性」の概念には注意が必要です。この文脈での安定性とは、結果の予測可能性を意味するものであり、技術的な簡便性を指すものではありません。非サッカロミセス系酵母の適切な使用には、従来以上の技術的理解と、より精密な管理が求められます。
発酵プロセスの各段階において、酵母の活動状況を注意深く監視し、必要に応じて適切な調整を行う技術力が不可欠です。温度管理、栄養補給、pH調整、酸素供給など、多岐にわたる要素を総合的に管理する能力が求められます。
今後の展望と技術革新の可能性
非サッカロミセス系酵母の分類に含まれる酵母の種類は極めて多様で、その数は膨大です。これらの酵母は使用方法によってワインに与える影響が大きく変化することが指摘されており、今後さらに多くの種類の非サッカロミセス系酵母が製品化され、従来とは異なる使用方法も提案されてくると予想されます。
興味深いことに、現在の技術動向では、非サッカロミセス系酵母の活用においてサッカロミセス系酵母との組み合わせ使用が推奨されています。正確な種類数が把握できないほど多様な非サッカロミセス系酵母を、同じく多種多様なサッカロミセス系酵母と組み合わせて使用するという状況が生まれています。
この組み合わせの多様性は、理論的には無限に近い可能性を秘めています。それぞれの組み合わせが独特の風味プロファイルを生み出す可能性があり、ワイン醸造技術の発展に新たな地平を開く可能性があります。
しかし、この多様性は同時に選択の複雑さも増大させます。生産者は、自らの目指すワインスタイルに最適な組み合わせを見つけるために、より深い理解と経験を積む必要があります。
ワイン造りに、あなたらしさを活かすパートナーを
栽培や醸造で感じる日々の疑問や不安を解消し、ワインの品質をさらに高めたい──
Nagi Winesは、あなたの想いとスタイルを尊重しながら、すべての工程をともに歩みます。
経験豊富な専門家が現場に入り、知識・技術・品質の向上を、実地作業を通じて支援。
費用を抑えつつも、あなたのワインらしさを守りながら確かなフォローを行います。
まずはお気軽にご相談ください。
結論:非サッカロミセス系酵母の本質的価値
非サッカロミセス系酵母とは、従来ワイン醸造の主流を占めてきたサッカロミセス系酵母以外のすべての酵母を包含する広義の概念です。これまでワイン醸造の現場で使用される機会は限られていましたが、それゆえに従来にはない独特の特徴を持つワインを創造するための有力な手段として注目を集めています。
これまでの醸造技術において、類似したアプローチとして自然発酵という手法が採用されてきました。この手法では、野生酵母や天然酵母と称される自然界に存在する酵母によってブドウ果汁を発酵させ、ワインを醸造します。確かに自然発酵では非サッカロミセス系酵母が関与する場合がありますが、サッカロミセス系酵母もまた自然界に存在するため、自然発酵が必ずしも非サッカロミセス系酵母による発酵を意味するわけではありません。
さらに、自然界には計り知れない種類の酵母が存在するため、非サッカロミセス系酵母であってもワインに害悪をもたらす酵母が活動してしまう可能性も少なくありません。
このような状況を受けて、特定の効果を得るために選別された非サッカロミセス系酵母を乾燥酵母として製品化する動きが本格化しています。これらの製品には、使用方法、注意点、期待される効果が明確に記載されています。このような酵母を利用することで、従来は自然発酵でのみ得ることができた特徴を、より低いリスクで、より効果的にワインに取り込むことが可能になりました。
現在、ワイン醸造の現場で利用機会が拡大している非サッカロミセス系酵母は、ワインに従来にない特性を付与しながら、同時に品質の予測可能性を向上させる新しい選択肢として位置づけられます。
確かに、そこには自然発酵が持つ偶然性による驚きはないかもしれません。しかし、自然発酵で遭遇する偶然性がすべて好ましいものであるとは限りません。そのような偶然性から好ましくない要素を排除していった結果は、商業化された非サッカロミセス系酵母製品によって実現されるワインに近いものになる可能性があります。
サッカロミセス系酵母は長年にわたる使用により過度に標準化され、それが新鮮味の欠如を招いた結果、非サッカロミセス系酵母に注目が移っています。しかし実際の応用では、非サッカロミセス系酵母とサッカロミセス系酵母の組み合わせ使用が推奨されています。そしてそうした組み合わせを通して、発酵を完了させる役割はサッカロミセス系酵母に委ねられています。ワインの発酵において、中心的役割は依然としてサッカロミセス系酵母なのです。
今までに使われてこなかった酵母の使用という、この技術的発展により、ワイン醸造の可能性はさらに拡大し、今後も継続的な進化が期待されます。非サッカロミセス系酵母の活用は、ワイン産業における技術革新の重要な一翼を担う存在として、その価値を高め続けていくことでしょう。