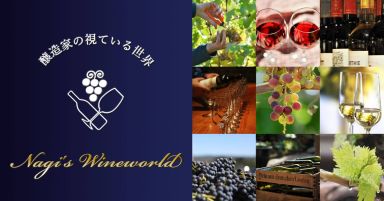ワイン造りにおいて発酵の管理はなによりも重要な工程の1つです。この発酵をどう進めるか次第で出来上がるワインは味も香りも変わってきます。
発酵管理というと発酵温度を何度くらいに設定するのか、速度をどのくらいにするのか、もしくはどのような酵母を使うのかに注目が集まりがちです。確かにこれらの項目は重要で、無視して発酵管理を行うことはできません。しかし、発酵を管理していく上ではもっと重要なポイントがあります。それは、発酵を止めないこと、です。
発酵は酵母の代謝によって進められる変化です。ブドウの果汁に市販の乾燥酵母を入れておけば、問題なく進むものと思われている場合もあるようですが、実はそこまで簡単なことでもありません。
酵母をはじめ、微生物の多くは気ままです。どのような方法を用いたとしても、100%安心で安全な絶対の手段というものは存在しません。とても不都合な真実なのですが、発酵はいつでも止まるリスクを抱えています。
発酵が途中で止まってしまう原因はいくつかあります。そうした原因の1つに含まれるのが、酵母です。
酵母は本来は発酵を進める立役者のはずなのに、その酵母が原因となって発酵が止まる可能性がある。あまりに矛盾しているように聞こえますが、事実です。この記事ではその一見矛盾した存在である、キラー酵母と呼ばれる酵母について解説をしていきます。
キラー酵母とはなんなのか
酵母には非常に多くの種類が存在しており、その分類にもいくつかの基準があります。例えば、サッカロミセス系酵母と非サッカロミセス系酵母という分類は、酵母の属に基づく分類です。
キラー酵母はそうした生物学的な属や種による分類ではなく、他の酵母を殺す特性を持っているかどうかに基づく分類です。周囲の酵母を殺す特性を持っていれば、その酵母がサッカロミセス系酵母であっても非サッカロミセス系酵母であっても、等しくキラー酵母として扱われます。なお、キラー酵母によって殺される酵母を感受性酵母、キラー酵母によって殺されることのない酵母を中性酵母と呼んでいます。
酵母の大部分は感受性酵母だと言われています。また感受性酵母は同時にキラー酵母であることが多く、Saccharomyces cerevisiae株ではおよそ50%がキラー活性を示したとする報告もあります。一方で、感受性酵母でありながらキラー性は持たない酵母も存在しています。なお、キラー酵母の割合は検証の環境条件によっても変動することが分かっており、絶対的な存在割合は分かっていません。
キラー酵母は1963年にイギリスで発見されました。研究や活用では現時点においてはワイン産業における展開が進んでいるとされていますが、キラー酵母自体は果実、花、樹、キノコ、土壌などからも見つかっており、まだ未発見の株の存在も含めて研究途上にある分野です。
分類と種類
キラー酵母はその酵母株の種類ではなく、キラートキシンと呼ばれる、他の酵母を殺す原因物質によって分類がなされています。
キラートキシンとは主に抗真菌性の化合物で、タンパク質、酵素、環状ペプチド、界面活性剤、揮発性低分子など多様な分子クラスタとして存在しています。これらの化合物はそれぞれの酵母が菌体内で生成し、それを菌体外に分泌することで標的となる酵母を攻撃します。
この物質の特徴は、酵母やその類縁菌に限定的に作用する点にあります。キラートキシンを生成する酵母は自身の作る毒性物質に対しては免疫を持ちますが、仮に免疫を持っていなかったとしても、そのキラートキシンの対象となっていない酵母には影響が出ません。この点において、攻撃対象を選別しない抗生物質とは作用の仕方が異なります。
キラートキシンの種類はそれを生成する酵母によって異なり、現在はそのタイプごとに分類されています。しかし、この分類はまだ主要なものにとどまっており、非サッカロミセス系酵母によるキラートキシンを含めた全体的な分類と体系化まではなされていません。
サッカロミセス系酵母が作るキラートキシン
現在の分類のなかでも、K1, K2, K28,そしてKlusと呼ばれる4つのタイプは特にSaccharomyces属の酵母に強く作用するキラータイプです。生産自体もSaccharomyces属の酵母によって行われています。
K1タイプはなかでもキラー活性が高く、ビールや清酒用酵母から分離されています。一方でこのタイプの酵母が作るキラートキシンはもっとも強い活性を示すpH範囲が4以上と高く、ワインにおける重要性は低いタイプでもあります。
これに対して、ワインで主に見つかっているのがK2と呼ばれるキラータイプです。このタイプの生産するキラートキシンは至適pHが2.8~4.8とワインのpHと一致しており、ワインにおける発酵がスタックする大きな原因とされています。
キラートキシンの標的特異性と影響の程度
キラー酵母を理解する上で重要なのが、同じキラータイプ同士は殺し合わないという点です。キラー酵母は自身が作り出すキラートキシンに対しては免疫を持ちます。このため、例えば同じK1のキラータイプに属する酵母Aと酵母Bが同じ液中に存在していたとしても、この両者にそれぞれの作るキラートキシンは作用しません。
また、それぞれのキラータイプはそれ以外のすべてのキラータイプを殺すわけでもない点には注意が必要です。
各キラータイプの作用対象には例外も存在しますが、例えばK1タイプやK2タイプはサッカロミセス系の感受性酵母に対しては作用する一方で、非サッカロミセス系の感受性酵母にはほとんど作用しないことが分かっています。しかしその一方で、自身のキラータイプ以外ではほぼすべてのキラータイプに属する感受性酵母に作用する、非常に広い効果範囲を持ったキラータイプの存在も報告されています。
作用範囲と脅威度は一致しない
なおキラートキシンの作用範囲と作用強度は必ずしも一致しません。K1タイプもK2タイプもサッカロミセス系の感受性酵母に作用しますが、K1タイプはK2タイプよりも作用強度が高く、強いキラー活性を示すことが分かっています。同様に、ほぼすべてのタイプに作用はするものの、K1やK2タイプに対する作用強度が低いために、実際にはこれらのタイプに属するサッカロミセス系の感受性酵母にとってほとんど脅威とならないキラートキシンを生産するキラー酵母も存在します。
自身のタイプに作用するキラートキシンを生産するキラー酵母だからといって、必ずしもリスクが高いとは限らないのです。
なお、サッカロミセス系酵母よりも非サッカロミセス系酵母の生産するキラートキシンの方が高いキラー活性を示す傾向が強いことが報告されています。またこれらの酵母の作るキラートキシンは安定性が高いものが多く、長期間にわたって作用する可能性が指摘されています。非サッカロミセス系酵母が生産するキラートキシンはサッカロミセス系の感受性酵母に対するキラー活性を示す場合も多く、発酵管理上のリスクとなりやすい特徴があります。
非サッカロミセス系酵母が主体となる自然発酵を行った場合にその後のサッカロミセス系酵母によるアルコール発酵がスタックしやすい原因の1つが、この非サッカロミセス系酵母が生成・分泌したキラートキシンによってサッカロミセス系酵母の増殖が阻害されることにあると考えられます。
作用機序と作用の内容
キラー酵母が分泌したキラートキシンがどのように作用しているのかの詳細はまだ明確にはなっていません。そうしたなかで、特に研究が進んでいるのがK1タイプの作用機序です。
K1キラートキシンは感受性酵母の細胞壁に含まれる(1-6)-β-D-グルカンを受容体として結合することが分かっています。この結合は選択的に行われているため、結合の対象となる(1-6)-β-D-グルカンを細胞壁に持つかどうかが、K1タイプが作用するかどうかの1つの選択基準となります。
細胞壁に結合したトキシンはその後、細胞膜に導入され、細胞膜中にイオン透過性チャネルを形成します。そうするとその透過性チャネルを通ってカリウムイオンやATPといった細胞内物質が漏出しはじめ、細胞死の原因となります。
K1タイプは主に細胞膜の機能破壊によって対象となる感受性酵母を殺しますが、他のキラータイプではそれぞれ異なる機序によって作用対象となる酵母を殺すことが分かっています。そうした方法には、特定の酵素の活性を阻害するケースや細胞壁のグルカン合成を阻害するケース、DNA合成を阻害するケースなどが報告されています。
影響の出方は一定しない
キラートキシンの作用はpH依存性が極めて高いことが分かっています。活性度に影響する至適pHの存在に加え、pHによってトキシン自体の構造や機能が変わる可能性が指摘されています。またそうした各種条件により、どの程度の割合でキラー酵母が存在すればそのキラー酵母が優占となるのかも変化すると考えられています。
キラートキシンの有効濃度を確保するためにはキラー酵母の細胞密度が一定以上になる必要があります。一方で、そうした優占確保のための初期細胞濃度がどの程度必要なのかについては条件依存性が強く、詳細が分かっていません。
S.cerevisiaeの場合では初期濃度が0.01~10%程度でキラー酵母が優占となったとする報告がある一方で、初期比率が1%程度ではキラー効果が発揮されず、2~6%が最小初期比率であるとする報告もあります。またキラー株が50%以上ではじめて優占となったとする事例もあります。キラー酵母が他の酵母を圧倒するために必要とされる初期濃度がどの程度なのかについては今後の課題といえますが、同時に発酵管理上は、不確定要素として常にキラー酵母が優占をとる可能性があることを認識しておく必要があります。
キラー性はウイルス由来
酵母の自身の細胞内で生成しているキラートキシンですが、その由来にはいくつかの種類があることが分かっています。
主にサッカロミセス系酵母が関連するタイプのキラートキシン生成には2種類のdsRNAプラスミドが関わっていることが知られています。これはLdsRNAとMdsRNAで、それぞれがMウイルスとL-Aウイルスに由来したdsRNAであるとされています。機能的にはMdsRNAがキラー表現型に直接関わる役割を担っており、LdsRNAは外皮タンパク質をコードする役割を担っています。
酵母の細胞内には非感染性のウイルス様粒子 (VLP) が存在しており、そのVLPがキラートキシンの生成を行っていると考えられています。なおこのVLPは酵母の増殖によって継代伝搬されており、外部からの新規感染は観察されていません。キラートキシンの存在は酵母にとっても自身の生存戦略上、重要な役割を持っているため、進化の過程でウイルスとの中立的共存関係が成立し、今でもその関係が続いているものと考えられます。
なお、dsRNAプラスミドに依存しない、核遺伝子に直接生成が支配されているキラータイプも確認されているほか、S.cerevisiaeから検出されたキラータイプであってもMdsRNAを持たない新しいキラータイプが発見されるなど、現時点で未発見のキラータイプも多く存在していると考えられています。
キラートキシンを予防する方法
キラートキシンによる影響を回避する方法はいくつかあります。キラートキシンはpHや熱に対して不安定であることが多いため、pHを調整したり加熱することでキラートキシンを失活させることができます。また、キラートキシンの多くはタンパク質系の化合物であるため、ベントナイトなどを添加することで吸着し、影響を抑制することも可能です。
しかしその一方で、キラートキシンは酵母が代謝の過程で分泌するため、一時的に失活させたり吸着させたりするだけでは不十分です。発酵工程全体を通してリスクを排除するためには、酵母が代謝を行っている間は継続して対処する必要があります。
そこで開発されているのが、耐性酵母です。
例えばVIN13などの商業酵母は育種を通して特定のタイプのトキシンに対する耐性を獲得しています。そうした調整により、同様のタイプのキラー酵母が存在する可能性の高い発酵工程中においても高い発酵安定性を確保することができるとされています。最近では既存の酵母にキラープラスミドを導入した製品や、逆に耐性を持たせた製品の流通なども拡大する傾向をみせています。
キラートキシンの影響を回避するには、キラータイプに影響されない中性酵母を使用することも有効です。一方で、酵母全体では感受性酵母の割合が比較的多いため、中性酵母だけを使用しようとすると選択肢が狭まる可能性が高くなります。
ワイン醸造におけるキラー酵母の意味
ワイン醸造におけるキラー酵母の影響は2つの視点から考えることができます。1つは、K2タイプに強く作用するキラータイプの発酵プロセスへの混入です。
これは例えば、主に非サッカロミセス系酵母であるWickerhamonyces anomalus (旧Hansenula属)などの酵母が該当するタイプのキラー酵母などが該当します。このタイプのキラー酵母はサッカロミセス系酵母に対して高いキラー性をもっているため、仮に混入した場合、サッカロミセス系酵母による発酵がスタックするリスクが高くなります。
2つめはスパークリングワインなどで二次発酵する場合における発酵への影響です。
初期発酵時にキラー酵母によって分泌されたキラートキシンは何らかの手法で除去しない限り、ワイン中に残存しています。このため、仮にベースワインの発酵時にK2に作用するタイプのキラー酵母が使用されていた場合、そのベースワインをK2タイプの酵母で二次発酵させることは難しくなります。最近では敢えてそうした組み合わせを選ぶ方法も検討されてはいますが、発酵管理上のリスクは高くなります。
どちらのケースにおいても、一度スタックした発酵を再開するためにはタイプの異なる酵母やキラータイプに影響されない中性酵母を使用するか、液中からキラートキシンを除去することが必要になります。
ワイン造りに、あなたらしさを活かすパートナーを
栽培や醸造で感じる日々の疑問や不安を解消し、ワインの品質をさらに高めたい──
Nagi Winesは、あなたの想いとスタイルを尊重しながら、すべての工程をともに歩みます。
経験豊富な専門家が現場に入り、知識・技術・品質の向上を、実地作業を通じて支援。
費用を抑えつつも、あなたのワインらしさを守りながら確かなフォローを行います。
まずはお気軽にご相談ください。
キラー酵母の利用は進むのか
酵母の増殖を阻害し、発酵を不安定にさせると聞くとキラー酵母は悪者のように感じてしまいますが、実際には醸造の現場では以前から上手く利用されてきた背景があります。例えば清酒の醸造現場ではキラー酵母を使って野生酵母を抑制することなどが行われてきました。キラー酵母には、利用したい酵母を殺してしまうリスクと同時に、存在してほしくない酵母を排除するメリットがあるのです。
また醸造の現場以外でも、キラートキシンの活用が検討されています。例えばキラー酵母が産生するキラートキシンには、抗真菌剤耐性を回避して食料安全保障を得るための役割が期待されています。
食料作物の栽培では、真菌類による作物損失が20%を超えているとされています。現在も防除は行われていますが、従来の薬剤は耐性菌の発生や対象外への影響といったオフターゲットの問題が指摘されています。これに対して、特定の対象により選択的に作用するキラートキシンは新しい生物防除剤として大きなメリットがあるのではないかと考えられているのです。
現時点においては生産効率が悪く、またpHや熱安定性をはじめとした使用・保管条件上の制約が大きいため利用は進んでいません。しかし、今後の研究開発次第では利用シーンが大きく拡大していく可能性がある分野と目されています。
酒類の発酵の現場でも醸造環境の変化により、発酵挙動の変化が出てくる可能性があります。そうしたなかで、より安定した発酵を得るための手段の1つとしてキラー酵母の積極利用が求められる可能性があります。そうした際には、周辺産業での利用が拡大すれば必ずしも酵母としてではなく、製剤としての利用可能性も出てくることが期待されます。そうなれば、使用上の利便性はかなり高くなると予想できます。
今後の研究開発の進展から目が離せません。