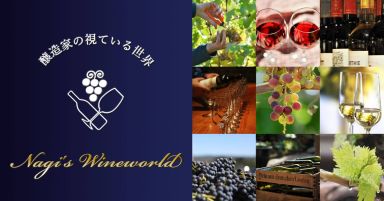ブドウ栽培の現場は、さまざまな病気との闘いの最前線でもあります。ブドウの病気といえばベト病やうどんこ病、灰色カビ病などが有名ですが、実際にはそれだけに留まらない、数多くの病気に栽培家達は日々悩まされています。
そうした病気のなかで、最近話題に上ることが多いのが、ウイルスによる病気です。
ウイルスによる病気といえば、インフルエンザや肝炎などがすぐに思い浮かぶ方も多いでしょう。記憶に新しいCOVID-19も、ウイルスによって引き起こされた感染症の一例です。
このように、ウイルス性の病気は私たちにとって身近な存在ですが、それは植物の世界においても同様です。ワイン用ブドウにとっても、ウイルスは無縁ではありません。むしろ、その健全な生育や品質に深刻な影響を及ぼす脅威的な存在として、すぐ隣に控えています。
欧米では植栽されるブドウの苗木を厳密に管理することでウイルスの蔓延を抑制しています。一方で、そうした制度が整備されていない地域も残っています。そうした地域では、ウイルスの脅威は年々高まっています。
この記事では、ワイン用ブドウ栽培におけるウイルスの存在と、それらがもたらす病気、そして対策の可能性について解説していきます。
ウイルスとはなんなのか
ウイルスによる病気、もしくはウイルスフリーの苗木。そう聞いた時、このウイルスという単語を具体的に頭のなかでイメージすることができるでしょうか。
例えばインフルエンザを考えてみます。インフルエンザはワクチンを使った予防接種が行われていますが、毎年、このワクチンの型が当たった、もしくは外れたという話が話題に上ります。これは一口にインフルエンザといっても複数の型があり、ワクチンはその型に一致していないと効果がないことから、当たり外れという話になっています。これはつまり、ウイルスにも複数の種類が存在している、ことを意味しています。しかも同じインフルエンザウイルスに分類されるものであったとしても、その中身が同じとは限らないということです。
ウイルスは電子顕微鏡でしか見えないほど微少な感染性粒子です。生物か非生物かは論争が続いているそうですが、一般的には非生物と分類されています。
ウイルスは細胞構造を持っていません。通常は遺伝情報が含まれた、一本鎖もしくは二本鎖の核酸とそれを保護するタンパク質の殻から構成されています。自ら増殖することはできず、生きた宿主細胞に依存しています。細胞の代謝を操作して自身の構成要素を主に生産させるなどして増殖していきます。また自分自身で移動することもできず、伝播には移動を担うベクターの存在が必要となります。
ワイン用ブドウ栽培におけるウイルス
世界中でこれまでに70種類以上の異なるウイルスがブドウから分離され、20を超える種類に分類されています。
多様な種類のウイルスが存在していますが、これらのすべてが、すべてのブドウ品種にとって脅威になるわけではありません。特定のブドウ品種でのみ症状を引き起こすウイルスというものも存在しているからです。
また一部の疾病については、その症状の出方からウイルスが原因であると推測されているものの、まだそのウイルスが分離・同定されていないものも存在しています。加えて、ウイルスによる症状の現れ方や被害の程度はウイルスの種類、感染したブドウの品種、そして気候条件などによって大きく異なります。そのため、かつてはウイルス性疾病と考えられていた病気であっても、その一部が実は違う原因によるものであることが分かり、訂正されたりもしています。
ウイロイドによる病気の存在
かつてはウイルスによる病気と思われていながら、近年になって別の原因によるものであることが分かってきた病気があります。それらはウイロイド (Viroide) という、より単純な構造の感染性粒子によって引き起こされるものであることが分かってきました。
ウイロイドは環状の一本鎖核酸 (RNA) のみからなり、ウイルスとは違って保護的なタンパク質の外殻をもちません。1971年に発見されており、最小の植物病原体であることが知られています。
ブドウからはこれまでに5種類のウイロイドが検出されています。これらはいずれも種子伝染性であるため、一般にクローンで繁殖されているワイン用ブドウでは実用上の重要性は小さいとされています。しかしその一方で、ウイロイドは特定のウイルスと組み合わされることでブドウの症状発現に影響を与えることが分かっており、完全に無視して良い存在というわけでもありません。
ウイルス病による経済的被害とその種類
すでにブドウから検出されているウイルスの数からも分かるとおり、ウイルスを原因としたブドウの病気は多数あります。そうしたなかでも特に経済的な被害が大きい病気として知られているのが、ファンリーフ病 (Grapevine fanleaf)、リーフロール病 (Glapevine leafroll)、そしてルゴーズウッド症状 (rugose wood complex) です。
一方で、これらの病気も含めてブドウがかかるウイルス性の病気のすべてが必ずしも重篤な症状を引き起こすわけではありません。また、ウイルス病には間接的な被害をもたらすものもあり、経済的被害を正確に評価すること自体も簡単ではありません。
例えば苗木園では、ウイルス病に感染した接ぎ木をパートナーに用いた接ぎ木をすることにより、活着率が低下し、発根能力が損なわれることがあります。また、一般のブドウ畑では生育の低下が収量の減少や畑の利用年数の短縮につながり、収益性を低下させます。このほかにもブドウの成熟が遅れ、果汁糖度の低下につながることもウイルスに感染することによる被害として考えられます。
なお、ウイルスに感染することによるもっとも重要な被害の1つは、ウイルスに汚染された畑からは苗木を作るための原料を得ることができない点だといえます。
ファンリーフ病 (Grapevine fanleaf)
ファンリーフ病は複数のウイルスによって引き起こされる病気ですが、主な原因となるのはNapovirus属に分類される、直径約30nm程度のウイルス群です。Grapevine fanleaf virus (GFLV)、Arabis mosaic virus (ArMV)、そしてRaspberry ringspot virus (RpRSV) のcherry系統 (RpRSV-ch)がここに含まれます。また比較的稀で特定の産地に限定されるウイルスとして、RpRSVのgrapevine系統 (RpRSV-g)、Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)、Tomato black ring virus (TBRV) などもこの病気に関わるウイルスとして知られています。
なかでもGFLVはブドウにのみ存在し、世界中の伝統的なワイン用ブドウ栽培地域で広く分布しています。感染したブドウ品種やヴィンテージによっては収穫損失が50%を超えることさえあり、最も危険なブドウウイルスの1つとみなされている存在でもあります。ArMVは世界中の多くの植物から検出されていますが、ブドウにおいては特にヨーロッパのワイン栽培地域で広範な分布が確認されています。
この病気の進行は一般に潜行性であり、感染後数年間は症状がほとんど見られないか、非常に軽度のものに留まります。潜伏期間の長さはブドウの品種や原因となっているウイルスの種類、病気の進行段階によって大きく異なることが分かっています。またウイルスによるブドウの樹の衰退速度にも大きな差が見られます。
Nepovirusはブドウ畑の圏内に棲息する線虫 (Xiphiema属、Longidorus属、Paralongidorus属) によって伝播されます。またそれ以外では感染した樹を原料に使用した接ぎ木でも容易に感染が拡大していきます。一方で、剪定作業による伝播は生じないとされています。
GFLVによるファンリーフ病の典型的な症状には、発芽の遅延、生育不良や矮化、枝の奇形、節間の短縮、ジグザグ状の成長、2重節などのほか、1つの節から2本に枝分かれするような症状も見られます。また、葉が小型化する、鋭い鋸歯状になる、葉縁の切れ込みが深くなり奇形して歪む、そしてこの病気の名前の由来にもなっている、葉身が強く縮れて扇状の外観を呈するようになるなどといった症状があります。このほかにも、葉に点状または斑点状の淡色化が見られるようになるほか、房が小粒になる、花穂が開花後間もなく脱粒し始める花ぶるいの症状などもこの病気の特徴としてあげられます。
ファンリーフ病はヨーロッパ系ブドウ、アメリカ系ブドウ、種間交配品種のすべてが感染する可能性があります。
感染したブドウでは、初期は枝の生長や花穗の形成に影響は出ないものの、病気が進行すると成長不良に加えて葉身にモザイク状や線状、または斑点状の黄化で見られるようになるなど、典型的な症状がほぼ確実に現れるようになります。また品種間による感受性の違いも大きく、ゲビュルツトラミネールは非常に敏感に反応する一方で、ケルナーやリースリングなどは比較的感受性の弱い品種として知られています。台木用品種においては通常、病気がかなり進行してからはじめて、症状が現れるとされています。
ファンリーフ病に関連するウイルスは複数確認されていますが、RpRSV系統やSLRSV系統などでは比較的強い地域性が確認されているほか、TBRVなどではウイルスを媒介する昆虫の生息域に準じた感染が確認されているなど、そのすべてがすべてのブドウ生産地域において等しく問題になっているわけではありません。またケルナーがArMVに感染することでケルナー病と区別して呼ばれるほど特殊な症状を起こすなど、同じ原因ウイルスでありながら一部の品種で特異的な反応を引き起こす場合も確認されています。
ケルナー病
ケルナー病とはファンリーフ病の特殊な形態とみなされており、その原因となるウイルスはArabis mosaic virus (ArMV) です。病気の感染はファンリーフ病の場合と同じく、ArMVを媒介する線虫によって引き起こされます。
一般的なファンリーフ病への感染ではケルナーは葉に多少の症状を出す程度で済みますが、このケルナー病に罹患した場合には話がまったく変わります。ケルナー病が蔓延した畑では深刻な被害が生じる可能性があり、危険度が跳ね上がります。ドイツでは1980年前半から半ばにかけてこの病気が一部の生産地域で猛威を振るい、13~84%もの樹が枯死した結果、この品種の植栽面積の増加が停滞した原因の1つになったとされているほどです。
この病気はArMVとケルナーの組み合わせでのみ確認されています。ArMV自体には他のブドウ品種も感染しますが、この場合には一般的なファンリーフ病の範疇に留まり、ケルナーほど極端に反応することはありません。例えばリースリングなどは仮に感染したとしてもそこまで重篤な被害にはいたらないとされています。
ケルナー病の症状としてもっとも顕著なのは、水分と栄養の欠乏です。葉は小さく、黄白色になり、着果が非常に弱く、房が極端に小さくなります。樹の生長も弱くなります。また台木との接ぎ木箇所が目立って肥厚するようになります。
この病気の最も怖い点は、罹患した樹は1年から3年以内に枯死するところです。特に樹がストレス環境に置かれている場合には、しばしば突発的な枯死につながることもあります。
リーフロール病 (Glapevine leafroll)
リーフロールはよく知られたブドウの病気ですが、実際に世界で最も広く分布しているブドウのウイルス病と言われています。この病気に罹患した樹は生育不良を起こし収益性の低下につながるため、大きな経済的損失をもたらす原因となっています。
発症の原因となるのは主にClosterovirus属とAmpelovirus属に分類されるウイルス群です。これらのウイルスは直径は12nm程度、長さは1800nmから2200nm程度の比較的長い糸状の形状をしています。世界中でこれまでに9種類の関連ウイルス (Grapevine leafroll associated virus, GLRaV) が発見され、識別番号がつけられています。
分布には地域性が見られるとされていますが、例えばドイツではGLRaV-1が圧倒的に優勢である一方、GLRaV-2の重要性は低くなっています。日本ではGLRaV-3の発生例が多いと報告されています。
GLRaVの伝播もファンリーフ病と同様に接ぎ木による被害が大きいとされています。またリーフロールの関連ウイルスはカイガラムシによる媒介が行われることが分かっていますが、一方でファンリーフ病とは異なり、線虫による感染の可能性は排除されています。なおカイガラムシはGLRaV-1,-2,-3,-5のベクターであることが確認されています。
リーフロールの症状は初夏を過ぎたくらいの頃から少しずつ目立つようになり、秋になると明らかな病変として認識できるようになります。葉が下を向き、同時に色が緑から黄変、または濃赤色に不規則に変色し始めます。こうした変色は末期には大きな葉脈とその周辺のみが緑に残る程度まで進行します。一般に症状は最も古い葉から出始め、枝にそって徐々に上方に進行していきます。
病気の進行は気候に強く影響され、温暖な地域ほど早く進みます。多くの場合で感染直後には症状は見られず、数年してから樹勢の低下など生育不良をはじめとした症状が現れ始めます。症状の程度はブドウ品種だけではなく、原因となっているウイルスの種類によっても異なることが知られています。例えばGLRaV-1による症状はGLRaV-3によるものよりも早い段階で現れ始め、明らかに強く発現することが確認されています。
リーフロールもファンリーフと同様にすべての穂木および台木用ブドウ品種で感染しますが、アメリカ系品種ではSO4を例外として、病気の症状が表出しません。潜在感染した台木品種では、発根能力が低下する可能性が示唆されています。
リーフロールは非常に広い地域で感染が拡大されている一方、主にヨコバイによって媒介されるレッドブロッチ病という別のウイルス病と症状が非常によく似ており、この両者が取り違えて認識されることも少なくありません。この2つの病気は症状はよく似ているものの、原因となっているウイルスは全く別のものです。レッドブロッチ病はレッドブロッチ病関連ウイルス (Grapevine red blotch associated virus) によって引き起こされています。
またリーフロール病とファンリーフ病に同時に罹患する可能性もあり、そうした場合にはそれぞれの症状が劇症化する可能性が指摘されています。
ルゴーズウッドコンプレックス (rugose wood complex)
ルゴースウッドコンプレックスはその名前が示すとおり、複数の異なる症候群がまとめられた状態を指しています。現在は4つの症状がこの症候群に含まれています。
これらの病原体や病因はまだ部分的にしか解明されておらず、また、個々の症候群は特定の指標ブドウ品種で引き起こされる反応によって区別されています。ルゴースウッドコンプレックスは主に接ぎ木を介して拡散していると考えられていますが、関与している一部のウイルスに関しては様々な種類のカイガラムシがベクターとなっていることが確認されています。
現時点においてルゴースウッドコンプレックスとして認識されているのが、コルキーバーク (Corky bark)、Rupestris stem pitting (RSP)、Kober stem grooving (KSG)、LN 33 stem grooving (LNSG) です。コルキーバークはほとんどのヨーロッパ系品種では目立った症状の表出はなく軽度の生育不良に留まりますが、比較的感受性の高いGamay、Cabernet franc、Pinot noirなどの品種では穂木の接合部付近で木部がスポンジ状やゴム状のような感触になり、腫れが裂けが出るようになります。
コルキーバーク以外の症候群にしても基本的にはアメリカ系台木にのみ現れ、その症状も木部に限定されています。
Vitis viniferaではほとんどのケースで潜在感染に留まること、RSPなどはVitis rupenstrisやその交配種の台木でしか発症しないことなどから実質的な被害はそれほど大きくはないと考えられており、最近まで検疫対象とされていなかった国や地域もあります。一方でかつてはイタリアや南アフリカ、ギリシャなどでは14~35%程度の収量減や畑の全損の原因となったこともあり、経済損失の規模とリスクを考えても無視して良いウイルス病というわけでもありません。
原因となるウイルスにはGrapevine virus B (GVB)、Grapevine rupestris stem pitting associated virus (GRSPAV, Foveavirus属)、Grapevine virus A (GVA) などが候補として挙げられていますが、一部を除いて断定はされておらず、また、まったく原因ウイルスが見つかっていないケースもあります。
ブドウがかかるウイルス病にはこのほかにも多様な種類のものがあるほか、前述のウイロイドのような存在に加え、ピノグリウイルス (grapevine pinot gris virus) のように最近になって発見されるものもあります。まだ未発見のウイルスがどれだけ存在しているのかも分かっていないのが現状です。
ウイルス病への対策
ウイルス病への対策とは、その原因となっているウイルスへの対策に他なりません。ヒトの生活の中ではインフルエンザワクチンなどのような対抗手段が存在している病気もあれば、そうした対策がまだ何もない病気もあります。ブドウにおけるウイルス病への対策は、この後者、事実上、どの病気に対してもまったく対策がないのが現状です。
ヒトが予防接種するワクチンの効果を考えればこの理由は分かりやすくなります。ワクチンはそれ自体がウイルスを攻撃しているわけではありません。むしろワクチンとは弱毒化したウイルスです。
これを生体内に取り込むことで、その生体が元から持っている免疫システムを刺激し、ウイルスへの対抗手段としています。つまり、ウイルスへ対抗するのはウイルスに罹患した生体の持つ免疫システムであって、ワクチンではありません。このため、仮にワクチンを使用してブドウがウイルス病に対抗するためには、そもそもブドウの樹が免疫システムを保持していなければ何の意味も無いことになります。そしてブドウの樹は、そうした免疫システムを持っていません。
このことは同時に、一度ウイルスに罹患した場合、そのウイルスを撃退する方法がブドウの中には存在しないという意味でもあります。
免疫がない以上、ブドウがウイルス病に罹患した際に自然治癒することはあり得ません。一方で、植物補助剤を用いた直接的な対策方法も現在、見つかっていません。これはウイルスが生物のような代謝機構を持っていないことに大きく関係しています。
つまりウイルスに一度感染してしまえばすでに手遅れで、そうした樹は根から完全に抜根して処分するしかなくなります。ブドウ栽培においてウイルス病との闘いは、予防的または間接的な対策が決定的に重要なのです。
こうした対策の1つであり、もっとも重要とされているのが、健全な繁殖材料の使用です。いわゆるウイルスフリーの苗木の生産もこの対策に含まれます。ウイルスに感染していないことが100%保証される材料を用いて苗木を作り、その苗木でさらに接ぎ木原料を作り、というサイクルをまわしていくのがその内容です。
しかし樹だけがウイルスフリーになったとしても、それだけではあまり意味はありません。ウイルス病はその多くがベクターを介して感染を広げていきます。このため、畑にベクターが存在している状態が維持されていると、ウイルスフリーの苗木を植えても即座に再感染を引き起こし、対策が徒労に終わることになるからです。
こうしたことから、ウイルスフリーの苗木を植える畑では事前にベクターとなる線虫やカイガラムシなどの昆虫を排除しておくことが極めて重要となります。
ベクターの排除と併せて効果的なのが、植物衛生学的な対策などを通してウイルスに感染しているブドウを早い時点から排除していくこと、そして、再植する際には事前に確認されていたウイルス病に対して感受性の高い品種を植えないことです。例えばケルナー病が確認されていた圃場であれば、ケルナーは再植せず、この病気に対して感受性の低いリースリングを植えるといったような対策が挙げられます。
ワイン造りに、あなたらしさを活かすパートナーを
栽培や醸造で感じる日々の疑問や不安を解消し、ワインの品質をさらに高めたい──
Nagi Winesは、あなたの想いとスタイルを尊重しながら、すべての工程をともに歩みます。
経験豊富な専門家が現場に入り、知識・技術・品質の向上を、実地作業を通じて支援。
費用を抑えつつも、あなたのワインらしさを守りながら確かなフォローを行います。
まずはお気軽にご相談ください。
今回のまとめ|まずは現状の正確な確認が必要
ウイルス病の非常に厄介な点は2つあります。1つは畑の外観からだけでは正確な状態の判別がほぼまったくつかない点です。
例えば末期のリーフロール病にかかっている畑であればその見た目である程度の検討がつきます。しかしそれでも、それが本当にリーフロール病なのか、実はレッドブロッチ病なのかは分かりません。症状が本格的に表出していないような段階ではなおさらです。正確な診断にはPCRによる遺伝子検査が必須となります。
ウイルスの同定方法としてはELISA法という簡易的な手法もありますが、簡易的な分、正確性に欠く部分があることが知られています。ELISA法では検出ができない場合もあるため、確実な観察にはPCRの利用が欠かせないのが現状です。
最近ではより簡易にPCR検査ができるポータブルな装置やDNAシークエンサーなどの開発も進んできてはいますが、ワイナリーが自身で個別に検査をするのが当たり前と言うにはまだ難しい状況です。検査装置以外ではウイルス耐候性の高い台木の開発なども進められています。今後、どれだけ畑のウイルス感染確認が容易になるのかに期待されます。
2つめは、一部の栽培家達から必ずしもウイルス病が悪いものとして認識されていない点です。
ウイルス病にかかった樹では生育不良が発生するケースが多くあります。以前であれば生育不良は即ブドウ果汁の低下などにつながり、最終的なワイン品質の低下につながっていました。しかし最近では、こうした状況に変化が生じてきています。
気候変動を背景に、ブドウの生育は早期化を続けています。このためブドウの栽培家たちは少しでもブドウの熟成を遅らせようと躍起になっています。ウイルス病は、こうした希望を一面的には叶えてしまうのです。
ファンリーフ病やリーフロール病に罹患したブドウではブドウの成熟が遅れます。実際は成熟が遅れているのではなく、生理不良を起こしているのですが、少なくとも表面的な果汁糖度の上昇は抑制されます。一方で、最近の天候状況では従来よりも収穫を遅らせることで、こうした成熟の遅れを補う程度の果汁糖度の確保が不可能ではありません。つまり、ウイルス病への罹患はある意味で都合の良い状況を生み出すことになります。そして、そうした状況が対策を遅らせることにつながります。
ウイルス性の病気は変則的で、あらゆる意味で予想や見通しが立て難いものです。症状が表出していないために罹患していることに気がつかず、気づいたときには畑の大部分が取り返しのつかないところまでいっていた、なんてことも十分にあり得ます。最悪の場合、ブドウの樹が大量に突然死する可能性さえあることを忘れるべきではありません。
すでに見てきたように、ウイルス病は一度かかってしまえばそこからの対策は何もありません。自身の畑にウイルスを持ち込まない、持ち込ませないことが何よりも重要な対策となります。そしてそのためには、すでにウイルスが入ってしまっているのであれば、その排除もしなければならないということです。
ベクター、特に線虫の排除などには時間がかかります。そうした対策の時間を生み出すためにも、効果的に対策を行っていくためにも、まずは現状を知ることが何よりも大事です。また、ウイルスは移動するものであり、一度の検査がその後も安心を担保することは残念ながらありません。
定期的な検査と対策の検討、そして実施が求められます。