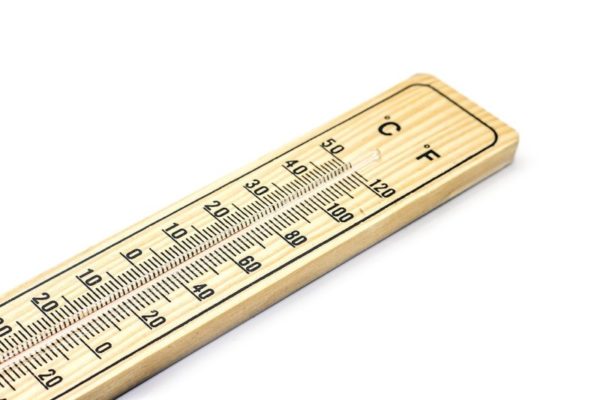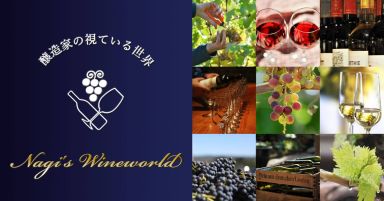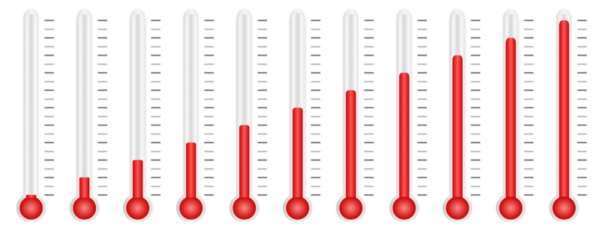
ワインの醸造を行っていく場合に、ブドウを絞ったジュースや発酵後もしくは発酵中のワインの温度を意図的に上げたり下げたりすることがあります。
ジュースやワインの温度を下げるケースに関しては、「発酵途中の温度管理 – 液温を下げる」という記事でまとめました。
-
-
発酵途中の温度管理 | 液温を下げる
白ワインの発酵は低温でする。 こんな話を聞いたことがある方、多いのではないでしょうか。ではなぜ白ワインは発酵を低温でするのでしょうか。赤ワインでは温度を下げなくてもいいのでしょうか。おそらくこうした疑 …
続きを見る
今回はこのケースとは逆のケース、温度を上げる場合についてそのタイミングと設定する温度について解説します。
発酵前に液温を上げる手法はもちろん白ワインの醸造においても意味を持つものですが、特に赤ワインの醸造において大きな意味を持ちます。中でもブドウの健康状態を確保しにくい地域においては有効な手段となりえるものですので、技術の一つとして知っておくことには大きな意味があります。
主に赤ワインの醸造で使われる高温処理
ワイン醸造において温度を引き上げるケースというのはそれほど多くはありません。温度を上げてしまうと各種雑菌や酵素の活動が活発になってしまい、結果として望ましくない影響が出ることが多いためです。
この一方で矛盾しているようではありますが、製造過程において加温処理を行うことは赤ワインの醸造においては比較的一般的な手法であるともいえます。
これは温度を上げることが色素をはじめとした各種成分の抽出に役立つためです。
醸造時に行う高温処理ですが、その加熱の程度によっていくつか種類があります。
- 短時間低加温処理: ~16℃程度。高くても20℃まで
- 長時間加温処理: 60~70℃程度
- 加熱処理: 80~87℃程度
それぞれの処理は使い所とその目的が大きく異なります。それぞれの詳細を見ていきます。
[circlecard]
発酵を補助する低加温処理
低加温処理は主に発酵の促進を目的として使用されます。
北半球でブドウを収穫する9~10月はまだ一般に気温が高く、破砕もしくはプレスしたジュースを発酵させるのに困ることはそうそうありません。むしろ液温が上がってしまうことを嫌って、温度を下げる方向で調整をすることがほとんどです。
しかし天候によってはブドウの収穫時にすでに外気温が下がってしまっている場合などもあり、自然な発酵のスタートが得られない場合があります。
このような場合に液温を16~20℃程度に一時的に加温することで酵母を活性化させ、発酵の開始を促すのです。一度発酵がスタートした後は発酵熱によって液温が上がるため、それ以上の加熱の必要はありません。
逆に液温を上げすぎてしまうと発酵が暴走する可能性があるため注意が必要です。発酵の暴走については「発酵について語ろう」の記事でも書いています。
-
-
発酵について語ろう
今までに発酵を実質的に引き起こしている存在である酵母などについてはお話をしてきましたが、発酵それ自体については説明をしたことがなかったので、この機会に改めて発酵というものについて書いてみたいと思います …
続きを見る
またこの手法は発酵が中断してしまった場合や極端に弱くなってしまった場合などに再発酵を促す目的でも使用されます。
ポイント
加温は
- 白ワイン: 16℃前後
- 赤ワイン: 20℃前後
- 発酵が開始するまでの短時間
色素の抽出に利用される長時間加温処理
ブドウの実を破砕した状態のマスト(Must、日本語訳: もろみ) を60℃以上に加温し、その温度を3~12時間保持するこの加温手法は、主に赤ワインの醸造時に色素の抽出を促進するのに利用されます。
加温上限は70℃程度までで、温度を上げるほど色素やタンニン、抽出物の抽出量が増えます。
なおこの手法における注意点は、60℃以下の温度では酸化酵素の活動が完全に抑制されないためかえって色素を低下させてしまうことにつながる点です。
ポイント
- 温度は60℃以上!
- 温度保持は3~12時間
- 70℃くらいまで
殺菌を目的とした加熱処理
液温を80℃以上に加熱するこの手法は、主に殺菌を目的として利用されることが多い手法です。
加熱をどの時点で行うかによって工程がことなり、得られる効果も変わります。例えばマストの段階で行う場合には80℃以上への加熱後にさらに一定時間、液温を高温状態に保つことで
- 色素およびフェノールの抽出量を増やし、質的にも向上させる
- 酸化酵素の活動を抑制し、酵素による酸化を防止する
- アルコールの揮発量を抑制する
といったような効果を得ることができます。
[Ad-innen]
逆にプレスをして清澄を終えた状態で加熱処理を行う場合にはより殺菌としての意味合いが強くなります。特に余計な酵母による発酵を完全に除外できるためにSO2の必要添加量を引き下げることが出来る点は注目に値します。
これ以外にも乳酸菌や酸化酵素の非活性化などによりワインの味わいに雑味が入ることを防止したり、酵素による酸化を防止したりすることが出来る点もこの手法の特徴です。
ポイント
加熱するタイミングはプレスの前か後
- プレス前: 高温短時間+温度保持
- 抽出の促進および酵素の無活性化
- プレス後: 高温短時間
- 衛生状態の向上、SO2の必要添加量の低減
加熱処理のメリット | 醸造工程の短縮
特に赤ワインの醸造において、加温・加熱処理を行うことは一定のメリットがあります。
赤ワインの醸造工程においてブドウの実を破砕し、そこで得られたジュースに果皮や種を一緒に漬け込んだまま発酵させるマセレーション (Maceration、日本語訳: 醸し) と呼ばれる工程は果皮及び種に含まれる色素やフェノール分の抽出を目的としています。
一方で加温・加熱処理をした場合にはこの工程中で十分な量の色素やフェノール分を抽出することができますので、改めてマセレーションの工程を入れる必要がありません。つまり、即時プレスし発酵工程に入るという、白ワインと同じ醸造工程を取ることが可能となります。
マセレーションの工程は数時間から数日という時間を必要としますので、この工程を削減できるということは醸造に必要となる時間を大幅に削減することに繋がります。
[Ad-innen]
醸造時間を短縮することの意味
昨今の気候変動の影響で収穫時期の気温が上昇したことに加え、収穫期に長雨が降ることが増えたためにボトリティス (Botrytis、日本名: 灰カビ病) への感染や野生酵母、カビ、バクテリア等によるブドウ品質の低下が懸念されています。これらへの感染などによって果汁のpH値が上昇する傾向にあり、結果としてSO2の効果が低下する悪循環が起きています。
SO2の持つ意味と使用方法については「品質管理のキホンのキ | 二酸化硫黄の使い方」でまとめています。
-
-
品質管理のキホンのキ | 二酸化硫黄の使い方
ワイン醸造における品質管理を考える際にもっとも基本となることは亜硫酸の添加です。 この亜硫酸、亜硫酸塩、酸化防止剤などともラベル上で記載されています。亜硫酸と亜硫酸塩とでは厳密には異なる物質を指してい …
続きを見る
この問題への対策としてはブドウの収穫から発酵までの加工時間を極力短くすることです。この時間が長くなればなるほど、カビや細菌による影響を大きく受けることになるためです。
そしてこのような事情がある中で、数日以上の時間を必要とするマセレーションの工程は多大なリスクをはらみます。そのようなリスクを避けることに対してこの加温・加熱という手法が意味を持つのです。