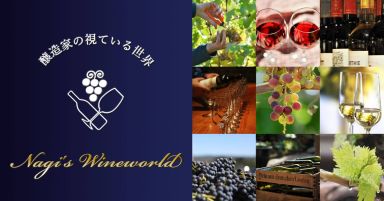ワインに関する記事の中で“香りの種類”と聞いたら、大概の人が想像するのはまずワインから漂う香りの種類のことだと思います。このワインからは青いりんごの香りがする、とか、干し草のような香り、とかいうあれです。しかし、今回のテーマである“香りの種類”というのはこのことではありません。その香りがワインの中に生成されたタイミングで区分された、“香りの種類”です。
香りの分類とその由来
今回テーマにしている意味での香りの種類は、多くの場合以下の3つに分類されることが多いようです。
- 第1アロマ: ワインの原料となるブドウに由来した香り
- 第2アロマ: 醸造過程において酵母や乳酸菌の活動によって生み出された香り
- 第3アロマ: 発酵完了後のワインの熟成・保管過程で発生する香り。ブーケともいう
一方で、醸造的には上記のアロマの区分をもう1段階細かく分けることがあります。つまり、
- 第1アロマ: ブドウ由来の香り
- 第2アロマ: 発酵工程前の作業段階において生じる香り
- 第3アロマ: 発酵工程中に酵母や乳酸菌の活動によって付与される香り
- 第4アロマ: ワインの熟成・保管過程において発生する香り
という区分です。なお、ここでは日本語に翻訳する関係上、敢えて上記区分と同じように“第○アロマ”、という表現方法を使っていますが、実際にはあまりこのような言い方では使われていません。本Blogでも以降は両者を区別するため、後者の区分における各アロマを第1のものから順に、品種香、加工香、発酵香、熟成香としたいと思います。なお、この名称はあくまでも本Blogでのみ使用するものであることにご注意ください。
醸造面でより重要視される香りの区分
後者の区分はソムリエ試験などで学ばれている区分とは異なっているはずですし、耳にしたこともないのではないかと思います。この区分はワインの製造工程の各段階において生じる可能性のある香りを細分化して捉えるものであり、より醸造家の側によった見方ともいえます。実際に発酵前の段階でブドウをどのように扱ったかによってその後のワインの香りが変わることはすでに分かっているため、ワインメーカーとしてはこちらの区分の方が都合がいいのです。これはマセレーション由来の香りの存在を考えていただければわかりやすいかと思います。
加工香がより注目される傾向?
以前の記事で書いたように、ワインメーカーの中には従来表現されていた品種香や発酵香だけでは自分の個性を表現できないと考え、より加工香や発酵香でも従来とは異なった種類の発酵香を求めるような動きが強くなってきているように感じることが多くなってきました。香りの構成はワインの特徴を決定付ける上で非常に重要なファクターとなります。このため、醸造家はどのような香りがどの過程の、どのような行動によって得られるものであるのかを熟知し、自身のワインに表現していくことが極めて重要となるのです。
ワインの個性を出す、ワインの味わいを作るということにに関する記事はこちら。
関連おすすめ記事