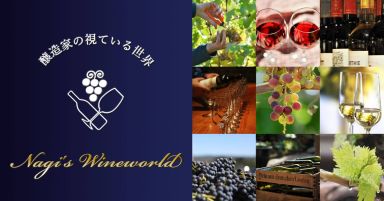聞き手: ヒマワイン (ワインブロガー) Twitter: https://twitter.com/hima_wine
サイト: ヒマだしワインのむ。
話し手: Nagi (醸造家) Twitter: https://twitter.com/Gensyo
Youtubeチャンネル | Nagiさんと、ワインについてかんがえる。
ワインブロガーであるヒマワイン氏と当サイトの運営者であるワイン醸造家のNagiがワインについて語り合うオンライン企画、”Nagiさんと、ワインついてかんがえる。”。
第32回のテーマはワインのフルーティーさ。
ワインを飲んでいたりおすすめのワインを聞いたりするとよく耳にするのが、このワインは果実味があって、といったコメントです。ワインはそもそもブドウから造られているお酒。果実味があるのは当たり前のように思えるのに、わざわざ「果実味があって」というのもおかしな表現のように感じたことはないでしょうか。
ワインの味や香りに対して果実味やフルーティーといった表現はよく使わるものですが、それがなにをさしている表現なのかはあまり厳密に意識されていないことも少なくありません。身近で共感を得やすい表現であるだけに、なんとなく、で使っても通じてしまうのがそうした使い方の背景にあります。
果実味という表現は正しい表現なのか、フルーティーさとは味で感じるものなのか匂いで感じるものなのか。そもそもどういった理由から我々はワインを飲むときにそうした感想を抱いているのか。造り手は意図的に果実味やフルーティーさを強くしたワインを造ることができるものなのか。数々の疑問に現役の醸造家が答えていきます。
チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
この動画に関連する記事
この動画の要約:この要約は生成AIを利用した要約のため動画の内容を正確に反映していない可能性があることを予めご了承ください。
フルーティーワインの製造における複雑さについて、ブドウの品種、収穫のタイミング、発酵方法、酵母の選択などの要因をカバーしています。フルーティーな香りと他のワインの特徴をバランスさせることが重要です。自然なワインとノンアルコールワインの味の類似点についても言及しています。フルーティーワインを作るには技術と慎重な考慮が必要です。