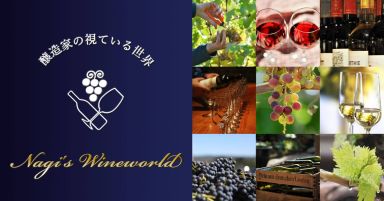棚に並んでいるワインのボトルを見ていると、実に様々な種類の栓を使ってボトルが密閉されていることがわかります。コルク、合成コルク、スクリューキャップなどなど。最近は技術の発展に併せてシリコン系のものも出てきています。
どんなワインにどんな栓を使うのか。
そこにどんな意味があるのか。
もしくはどんなワインにはどの栓を使えばいいのか。
ワインを楽しむ側も、造る側もそんな疑問を持ったことがあるのではないでしょうか?
ふと気になってデータを調べていたところ、少し古いですが2017年にドイツで使われていた栓の種類とその使われ方の傾向に関する記事が見つかったので紹介したいと思います。
この記事を読んでいただければ、どんなワインにどの栓を使うのかが分かるようになります。
栓の選択には各地域における歴史的な背景もある
ニュージーランドに行くと、白ワインでも赤ワインでもほぼすべてのワインがスクリューキャップで閉じられています。価格帯の高いワインであってもこの傾向は同様で、高いワイン、特に高価格帯の赤ワインは天然コルクを使うもの、というイメージを持っていると驚かされます。
この理由は醸造的なものではなく、歴史的な背景によるものです。
かつてまだニュージーランドがワインの生産を拡大し始めた頃、生産者はフランスなどの歴史的なワイン生産国を見習い、天然コルクを使うことを選択していたそうです。
しかしこの時期にまだまだニュージーランドなどのワイン新興国を侮っていたコルクメーカーから品質の劣るコルクを掴まされてしまい、大規模なTCA被害で大変苦労をしたためにコルクの使用量が激減、国全体でほぼスクリューキャップを使う現在の状況になりました。
このような状況下では使う栓の種類に選択肢はあってないようなものなので、そういうもの、として納得するしかありません。
一方で、昔からワインを造っていた国においてはこのような人的要因に基づく被害の経験がないため、様々な理由から複数の異なる種類の栓を選択することが可能となっています。
調査データの詳細
今回の記事の執筆に際して参考としているデータは、ワインの評価を行っている、DLG-Bundesweinprämierung という団体のものです。データ自体は das deutsche Weinmagazin 2018年2月10日号に掲載された記事から引用しています。
このデータでは、各種の栓の使用状況を
- 栓の種類
- ワインの種類
- 生産地域
- ワインの等級
- ボトルのサイズ
- ボトルの種類
- 価格帯
の分野ごとにまとめています。
なおこの調査はドイツ国内で生産されているワイン全量を対象に調査したものではなく、2017年にDLGに寄せられた評価用サンプル4000種を対象にまとめられたものであることには注意が必要です。
[Ad-innen]
最も多く使われていたのはスクリューキャップ
この調査の対象となったワインでは、実に63%のワインでスクリューキャップが使われていました。これについで多かったのが天然コルクで24%でした。
なおここでいう“スクリューキャップ”とはBVS-longcapと呼ばれる長いタイプのもののみを指しています。一部のジュースの蓋などに見られるようなより簡易的な短いタイプのスクリューキャップはMCAといい、区別しています。

この両者で全体の9割弱を抑えてしまっており、その他の栓は多くても5%程度、ほとんどが1~3%程度の使用率にとどまりました。
スクリューキャップは以前から使用率が増える傾向にあります。
5年前に天然コルクを抜いて最も使用される栓の種類となってからもその伸び率こそ小さくなりはしたものの、依然として使用率は増加傾向にあります。
スクリューキャップが使用される理由としては以下のようなことが考えられます。
高い密閉性とそれに伴う酸化防止効果
安価であること
TCAフリーであること
開栓しやすく、再度閉めることが容易であること
特に最後の開けやすさ、閉めやすさは顧客側がスクリューキャップを受け入れる大きな要因となっています。この顧客側の受け入れ、というものがこのタイプの栓の利用拡大の大きな原因の1つであることは間違いありません。
高級なイメージを持つ天然コルク
安価、容易といったイメージが付いているスクリューキャップに対して、天然コルクはワイナリー側、顧客側ともに伝統的、高級といったイメージを持たれています。
特にこの調査ではコルクを抜くときの音に対して顧客側が良好なイメージを持っている、ともしています。こういったポジティブな感情的要因が天然コルクに対して良好なイメージをもたせ、そのイメージに沿ったワインに使われる、という循環が出来上がっています。
天然コルクの代替品として使われ始めているDIAMに代表されるような合成コルクは、今回の調査では全体の5%程度の使用率に留まりました。
[Ad-innen]
利用率のまだ低いガラスコルク
以前このサイトで記事にしたこともあるVinolockのようなガラスコルクの使用率は1%程度でした。ガラスコルクは性能面で優れており、スクリューキャップや天然コルクの代替候補として挙げられることも多いものですが、実際の使用率はまだ低いのが現状のようです。
-
-
コルクは呼吸をしない?
先日、とあるワイナリーのワインメーカーさんとお話しをさせていただいた際にとても興味深いお話を耳にしました。コルクが”呼吸をする”というのはまったくの間違いだ、というのです。 コルクが呼吸をするというの …
続きを見る
このタイプの栓の使用率がなかなか高まらない理由としては、以下のようなものが挙げられます。
値段が高い
ボトル、特に口の部分の形状が栓に適合している必要がある
ボトリング装置が対応している必要がある
ワイン生産地域における利用の傾向
今回の調査結果を見ていて特に面白いと感じたのが、この区分です。
Baden (バーデン) および Sachsen (ザクセン) では天然コルクの使用率が高い (それぞれ40%および51%)
Franken (フランケン) ではほぼスクリューキャップ
調査対象となったガラスコルクが使用されたボトルの37%はHessische Bergstraße (ヘッシッシェ ベルクシュトラーセ)のもので一番多く、次が4%のRheingau (ラインガウ)
Württemberg (ヴュルテンベルク) はMCAと呼ばれる短いタイプのスクリューキャップの利用が多く、今回の調査対象となったMCA利用の15%を占めている
Mosel (モーゼル) は最もスクリューキャップの使用率が低く、代わりに合成コルク系の利用が多い (合成コルクの25%、合成樹脂系コルクの26%がMoselから提出されたサンプルだった)
ワインの種類およびボトルの形状に基づく使い分け
ワインの種類とその造りによっても栓は使い分けられる傾向が見られました。
天然コルクは圧倒的に赤ワインに対して使われており、その使用率は白ワインの倍以上でした。
また赤ワインの中でも木樽を使った醸造をしているワインになるほど天然コルクの使用率は上がる傾向にあります。これは主に天然コルクによってもたらされるとされる、微小酸化による熟成への影響を考えての選択となっています。
一方でフレッシュさやフルーティーさを重要視する白ワインやロゼでは天然コルクの利用率は低く、圧倒的にスクリューキャップが使われていました。
どの形状のボトルを選ぶのか、という選択は一般的にそこに充填するワインのタイプによって決められます。
樽熟成をしたタイプの赤ワインであればブドウの品種に応じてブルグンダー型やボルドー型のボトルが選ばれますし、フランケンの白であればボックスボイテル、伝統的なラインガウの白はラインガウフルート、となります。
このため、自然とブルグンダー型やボルドー型のボトルに対しては天然コルクの利用率が高くなりますし、逆にボックスボイテルやラインガウフルートではその大半がスクリューキャップによる密閉がなされています。
ワインの等級とボトルの大きさ
ワインの等級が高くなると使われるボトルのサイズは小さくなる傾向があります。
BA (Beerenauslese: ベーレンアウスレーゼ) や Eiswein (アイスワイン)、TBA (Trockenbeerenauslese: トロッケンベーレンアウスレーゼ) などの高等級のワインは375 mlのハーフボトルに充填されることが多くなります。
こういった高等級のワインは価格帯も高くなるため、等級が高いもの、ボトルが小さいもの、そして価格が高いものほど天然コルクの使用率が高くなり、逆にKabinett (カビネット) やSpätlese (シュペートレーゼ) のなどはスクリューキャップが利用されることが多くなる傾向にあります。
このあたりはKabinettやSpätleseはワインの特徴としてもフレッシュ感やフルーティーさが重要なワインでもあることから、酸化を嫌うスクリューキャップを選択することは自然なこととも言えます。
[Ad-innen]
スクリューキャップはオフフレーバーフリーではない
ボトルの栓についてはどうしても天然コルクのTCAが目立つためこの点ばかりが問題視され、天然コルク以外のものを使うことが推奨されるような側面もあります。
しかし実際にはスクリューキャップや合成コルク類もオフフレーバーフリーではないことには注意が必要です。
今回の調査結果にも記載されていましたが、スクリューキャップを使用したワインの20.4%、合成コルクを使用したボトルのおよそ17~18%のものでコルク臭 (TCA) に似た、もしくはコルク臭とは違うもののカビっぽいような、はっきりしない異臭があったそうです。
ちなみに天然コルクを使用したボトルでは14.2%でしたので、数字の上ではスクリューキャップは天然コルクよりも遥かに危ないことになります。
この点ではガラスコルクが13.5%と最も低くなる結果となりました。
なお今回の調査はあくまでもその栓が使われていたボトルでオフフレーバーがあった、という統計をとっているだけで、そのオフフレーバーの原因が必ずしも栓の種類にあるわけではないことには注意が必要です。
もともとオフフレーバーが含まれていたワインをボトリングしており、そのボトルにたまたまスクリューキャップを使用する率が高かっただけ、という可能性があるのです。
特にそれぞれの栓にはその栓を使うワインのタイプにある程度の偏りがあります。
このため一定のカテゴリーにあたるワインで似通った傾向が出やすい、という可能性は十分にありえることです。
今回のまとめ
ワインのボトルの封をするために使われる栓には様々な種類がありますが、それぞれが一長一短を持っています。
特に天然コルクでなければオフフレーバー問題は生じない、という考えは明確な間違いであり、仮にスクリューキャップを使用した場合でもこの手のリスクは存在します。
その上で栓の選択は、
生産者のポリシー・嗜好
マーケティング・販売戦略
主要顧客層とそのタイプ
ワインメーカーの持つ醸造的視点
のそれぞれに基づいて行われており、これが絶対、という正解はないというのが現状です。