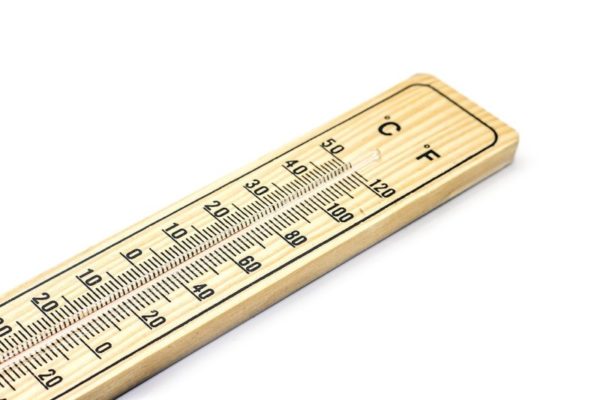ワイン造りは難しい。そう思ってはいないでしょうか。
確かにワイン造りを細かく見ていこうとすると、そこには微生物学の知識や化学の知識が必須です。ブドウの栽培からお話を始めると、ここにさらに植物生理学や土壌学、気象学、物理学など必要となる知識は増える一方。とてもワイン造りは簡単です、とはいいにくいのが実情です。
ただそんな細かい知識が求められるのは本職の人間だけ。ワイン造りの基礎を学ぶのであれば、このような知識は実は不要です。
むしろそんな面倒くさい話をされれば、人間、好きなものも嫌いになってしまうのが道理というもの。なので、この記事では可能な限りそうした面倒くさい部分に触れずに簡単にわかりやすく、ワインの造り方を解説してみたいと思います。そしてそのための方法が、"引き算"です。
では、"引き算でわかってしまうワインの造り方"のお話をはじめましょう。
ワインの基本は潰したブドウを置いておく
ワインというお酒をものすごく簡単に一言で説明すると、「ブドウを潰しておいておくと出来上がるお酒」です。
意外に思われるかもしれませんが、今も昔もこれがワイン造りの基本であることは全く変わっていません。現在ではワイン造りは「醸造学」という学問として確立されてはいますが、やっていることの大本は「ブドウを潰しておいておく」。これだけです。
これだけのことでワインが出来上がります。
ワインはこれだけで出来上がりますが、そのワインは色であったり、苦みであったり、青臭さであったりといろいろと含んでいます。なので、ここからいろいろないらないものを引いていきます。これを「醸造」といいます。
醸造で必要になる引き算のいろいろ
ワインの醸造ではいくつかのタイミングで引き算をします。そのタイミングはざっくり分けると以下のような区分になります。
- ブドウの収穫後 ~ 発酵前
- 発酵中
- 発酵後
順番にみていきます。
発酵前の引き算 | 色を引く
ワイン造りで必要になる最初の引き算は出来上がるワインの「色」と「味」に関する引き算です。
収穫してきたブドウを潰しておいておくと出来上がるワインでは色が濃くなります。その色が赤なのかオレンジっぽい色なのかは潰したブドウの種類によりますが、とにかく色は濃い感じです。
ここで醸造家は考えます。自分の頭の中にある出来上がり予想図に描かれたワインに必要な色は何色なのかな、と。
この時に必要になる色が濃い赤やオレンジだったら引き算は必要ありません。そのままブドウを潰しておいておけば予想図通りのワインが出来上がります。一方で、色がいらないな、となった場合には引き算をします。
この時に引くものは、ワインの色の原因となる「果皮」、ブドウの皮です。
-
-
徹底解説 | 赤ワインはなぜ赤いのか?
赤ワインはなぜ赤いのか? こんな疑問を持ったことがある人は多いのではないでしょうか? この疑問の回答を得るべく調べてみると、割と簡単に得られるのが以下のような情報です。 これは正しい回答です。 赤ワイ ...
続きを見る
-
-
徹底解説 | オレンジワインの造りかた
前回、「オレンジワインは自然派ワイン? | ワインあるある」と題した記事でオレンジワインの定義や成り立ち、どうしてオレンジワインが自然派ワインと同一視されやすい環境が出来上がってしまったのかといった点 ...
続きを見る
「果皮」を引く、といってもブドウの粒を一粒一粒皮をむくようなことはやってられません。そこで、ちょっと考えます。おいておく"潰したブドウ"から果皮を引いたら何が残っているのだろう、と。
ブドウを潰して、そこから果皮を抜いたら残っているのは果汁と種ですが、大体は果汁です。これ、逆説的に考えれば、果汁さえ取れればいいってことです。なので、醸造家は考えます。もっとも効率よく果汁「だけ」取れる方法でブドウを潰せば不要な色もなくなって一石二鳥じゃないか、と。
この"もっとも効率よく果汁を取るぶどうの潰し方"が、搾汁とかプレスと呼ばれる方法です。
色味が欲しい赤ワインやオレンジワインではブドウはいきなりプレスせずに「潰す」だけなのに、色味がいらない白ワインやブランドノワールではブドウをいきなり「搾る」のはこの引き算をしているかしていないかの違いなわけです。
発酵前の引き算 | 苦みを引く
何色のワインを造りたいかによって果皮を引くかどうかを決めました。でも、発酵の前にはもう一つ考えなければいけない引き算があります。
「苦み」です。
ワインの色に関わらず、苦みとか青みというような味の要素をワインに入れたいかどうか、やはり醸造家は考えます。ちょっとの苦みが欲しい、とか、苦みはまったくいらない、とか。その考え方は様々です。
とりあえず頭の中の完成予想図にあるワインでは苦みは軽いかほとんどなくていい、となった場合、引き算が必要です。ここで引くのは、梗と呼ばれる、ブドウの房にある緑の部分です。
色がいらないワインであれば梗は果皮と一緒に取り除いてしまうことができます。つまり、プレスに全部まとめていれてしまってそこから果汁だけ取り出す、というやり方をするのが一番簡単です。
一方で、色を残すワインでは果皮の部分は引いてしまっては困るので、梗の部分だけ引く必要があります。ここでやるのが、「除梗」と呼ばれる作業です。文字通り、ブドウの房から梗だけを取り除く作業で、果皮はそのまま残ります。
ちなみにこの梗、プレスに入れて搾ってしまうとちょっとだけ苦みが出てきてしまいます。このちょっとの苦みもいらないよ、という場合には引き算を二回に分けてやります。カッコをつけて先に計算させるような感じです。
さきに除梗だけして梗を引き、そのまま今度はプレスに入れて果皮を引きます。こうすることで梗から出てくる苦みをしっかりと引き算してやるのです。
発酵中の引き算 | 温度を引く
色や苦みの引き算を考えたら、次に醸造家が考える引き算は発酵中の引き算です。この時に一番大きな対象が「温度」です。
発酵中は酵母と呼ばれる微生物が活発に動きます。ヒトが運動をすると熱が上がるように、酵母も運動をすると熱を出します。これによって、発酵中の果汁の温度もあがります。
ワインに色を出したい場合、温度は高い方が色がたくさん出てきやすくなります。なので、引き算は必要ありません。ただ、温度が高いと揮発しやすい香りが蒸発していってしまいます。これは困ります。そこで、温度を引き算します。
温度を引き算する、と聞いてもわかりにくいかもしれません。
一般的にモノの温度はそのモノ自体が発熱をしていなければ環境温度と同じになります。ワインの場合は酵母が発熱していますので、発酵中の果汁の温度はもっと高くなります。そこで環境温度を下げることで上がっている状態の温度を「引く」のです。
この場合の「環境温度を引く」というのは、容器、つまりタンクの温度を下げる、ということです。
-
-
発酵途中の温度管理 | 液温を下げる
白ワインの発酵は低温でする。 こんな話を聞いたことがある方、多いのではないでしょうか。ではなぜ白ワインは発酵を低温でするのでしょうか。赤ワインでは温度を下げなくてもいいのでしょうか。おそらくこうした疑 ...
続きを見る
どこまで温度を「引く」のかは醸造家の頭の中のワイン完成予想図によって違います。なので、全く引き算をしない場合もあれば、大きく引き算をして冷たいくらいまで温度を下げる場合もあります。
発酵中の引き算 | 酸素を引く
発酵中の引き算にはもう一つあります。酸素です。
酸素はワインを劣化させる原因の一つですが、欠かすことのできない要素の一つでもあります。特に色のあるワインを造る場合にはある程度までは積極的に取り入れていくことも多くあるものです。
ただそうはいっても特に色がないワインでは酸素を多く入れてしまうと問題にしかならないので、引き算が必要です。ここで重要なのが、どれだけ引くのか、です。
酵母が増えるためには酸素はなくてはならないので、いくら引き算をするにしても完全に引ききってしまうわけにはいきません。また酸素の量をあまりにも引いてしまうと硫化系の嫌な臭い (これをオフフレーバーと呼びます) が出てくる原因にもなってしまいます。
-
-
もっと発酵を語ろう | 酸素は酵母に必要か
記事をお読みいただく前に この記事では説明の都合上、学術用語としての“発酵”と一般的なアルコール生成手段としての意味での“発酵”が同一文章内に特に断りなく混在して使用されています 何度か発酵についての ...
続きを見る
引き算の加減が難しい酸素ですが、やり方は簡単です。蓋のある容器に果汁を入れて発酵させておけば、酵母が排出する二酸化炭素ガスが容器内に充満するため勝手に酸素が抜けていくのです。
色が欲しいワインを造るときに開放型と呼ばれる、蓋のない容器を使うのはこのためでもあります。
発酵後の引き算 | 味と香りを引く
無事に発酵が終わってもまだ醸造家は引き算を考えます。次の引き算は味や香りに関わるものです。
昔、まだ現代的な技術が発達していなかった頃のワイン造りでは発酵前の果汁や発酵が終わってワインになった液体を入れる容器には木製の樽を使っていました。当時はこれが当たり前だったのですが、この当たり前に使われていた容器からワインの中に出てくる香りや味があることに気が付いた人がいました。樽香と呼ばれるものです。
とある醸造家の頭の中に描かれたワインの完成予想図ではこの樽香がいりませんでした。ではどうしようかと考えた彼のとった手段が、「木製の容器を引き算する」というものだったのです。
木製の容器を引いて、金属製の容器を使うことでワインから樽の香りや味が引かれました。でもまだワインの味や香りに影響を与えるモノが残っていました。発酵を終えて容器の底に沈殿していた酵母の死骸です。
酵母の死骸をそのまま容器の中に残しておくとワインにコクのようなものが出てきます。このコクのようなものが造る予定のワインの完成予想図に入っていれば引き算の必要はありませんが、すっきりとしてシャープな印象のワインを造りたいときにこうしたコクが邪魔だと思えば、その原因である酵母の死骸を引き算する必要があります。
その方法はろ過であったり完全に沈殿した状態から上澄み部分だけすくって別の容器に移す、というものだったりします。
発酵後の引き算 | 濁りを引く
発酵前、発酵中、発酵後。ここまでに様々なものを引いてきた結果、完成予想図にずいぶん近づいたワインが出来上がったはずです。でもまだ醸造家は引き算を考えます。このワインをボトリングする前にもっと引いておく方がいいものはないだろうか、と。
出来上がったワインをグラスにとってみると、何となく濁りが出ています。これをよしとするなら引き算は終わりです。そのままボトリングをしてお披露目です。
一方で濁っているのはちょっとな、と思った場合には最後にもう一度、引き算をします。濁りを引くための引き算です。
ワインから濁りをなくすためにはフィルターとも呼ばれるろ過の作業が必要です。このろ過の作業、種類はいくつかありますが、目的は一緒。ワインから濁りを引き、透明な状態にするためのものです。
-
-
濁ったワインは何が悪いのか
「濁りワイン」 日本では意外に市民権を得ている印象の強いワインのカテゴリーですが、これは日本独特な動きと言えます。 もちろん世界にも醸造過程を通してフィルターろ過を行わない「unfiltered」のワ ...
続きを見る
[Ad-innen]
今回のまとめ | 足し算のように見えるものも実は引き算で考えられる
ワイン造りには引き算ではなく、足し算の結果のように思えるものもあります。酵母や乳酸菌、酸化防止剤として知られる二酸化硫黄などです。
しかしこれらの利用もまた、基本的には引き算で考えた結果であることがあることがほとんどです。
野生酵母が生み出す可能性のある雑味や発酵の停滞や中断のリスクを引くために酵母を添加していますし、乳酸菌を添加しています。発酵をさせたいから、乳酸菌発酵を行いたいから入れているわけではなく、入れなくてもできるけれどそうすると余計なものまで入ってしまうので、その余計なものを引くために敢えて加えている、という考え方です。
これは立派な引き算です。
また何も引き算せず、潰したブドウを置いておいてできたワインには微生物なども引かれることなくそのまま残っています。こうした「引かれていないモノ」が持っているリスクを「引く」ために添加するのが二酸化硫黄、SO₂です。
予めワインの中から不要なものをしっかりと引き算していればそこから生まれるリスクも引かれているので、添加しなければいけないSO₂の量も引くことができるようになります。
-
-
品質管理のキホンのキ | 二酸化硫黄の使い方
ワイン醸造における品質管理を考える際にもっとも基本となることは亜硫酸の添加です。 この亜硫酸、亜硫酸塩、酸化防止剤などともラベル上で記載されています。亜硫酸と亜硫酸塩とでは厳密には異なる物質を指してい ...
続きを見る
-
-
二酸化硫黄、正しく理解していますか? 1
このBlogでも度々話題にしている二酸化硫黄、やはり注目度の高い話題のようで、多くの方に御覧頂いているようです。ただその一方で、この物質を正しく解説したものが少ないからなのか、この二酸化硫黄というもの ...
続きを見る
このようにワイン造りの基本はすべて「引き算」で考えることができます。
逆にこのような引き算ではどうやっても考えることができず、足し算で判断するしかないようなことがされているワインは消費者の方から避けられる傾向が強いようです。足し算が必ずしも低い品質の証明というわけではありませんが、何かが足りないからこそ足している、と考えられてしまうのもわからないことではありません。
実際にワインを造る場合に考えなければいけないことはいろいろあります。しかしその一番根底にある基本的な考え方として、必要なものがしっかりと入っているのであれば、あとはそこから不要なものを取り除くことで高品質のワインを造ることができる。これが最もシンプルなワイン造りの方法だといえます。
もっと詳しいワイン造りの方法を日本語の本で読んでみたい、という方はこちらの本を手に取ってみるのもいいかもしれません。