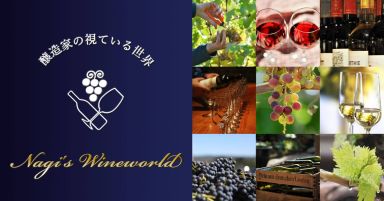ドイツワインのボトルに貼られたラベルを眺めていると、この国のワインではよく目にするのに他の国のワインではあまり見かけない情報が記載されていることに気がつきます。それは例えば、Buntsandstein、Löß、Muschelkalk、Schieferといったものです。皆さんはこれが何を指したものか、ご存知でしょうか。
これらはすべて、石の名前です。Buntsandsteinは色砂岩、Lößは風成シルト質堆積物である黄土、Muschelkalkは貝殻含有石灰岩、Schieferはスレートを意味します。こうした名前がワインのラベルに記載されている場合、そのワインに使用されたブドウ畑の土壌タイプの名前として理解されます。
ブドウ畑の土壌質についてはしばしば話題にされますし、その情報に重要性を見出す方も少なくありません。一方で畑の土壌タイプが直接ラベル上に記載されている例はドイツの例などを除けば、あまり多くないのが実情です。なぜドイツワインではしばしば土壌タイプがラベル上に記載されるのか。また、そうした情報にはどのような意味があるのか。2024年公開された研究の成果を基に見ていきます。
ドイツでラベルに土壌タイプが記載される理由
そもそもなぜドイツではボトルに貼られたラベル上に土壌タイプを記載することが多いのでしょうか。
最近はドイツでも栽培されるブドウ品種が以前のものから変わってきていますが、それでも中心品種は依然としてリースリング (Riesling) が占めています。ドイツワインインスティテュート (deutsches Weininstitut: DWI) が公表しているデータによると、リースリングは2023年に24,388 ha栽培されており、これはドイツの全栽培面積の23.5%に当たります。2位がシュペートブルグンダー (Spätburgunder) の11,519 haで11.1%ですから、いかにリースリングの栽培面積が大きいのかが分かります。
そんなリースリングですが、品種やワインの特徴から樽発酵や樽熟成、マロラクティック発酵などはあまり積極的に行われることはありません。そうした背景もあり、ドイツワインでは以前から醸造の影響を最小化し、環境の真正な表現が達成されていると信じられている側面が強く存在しています。ラベル上への土壌タイプの表記も、こうした流れの中で進められてきたものであると考えられています。つまりドイツワインにおける土壌タイプの表記は、テロワールを表現する簡略化された記号であると同時に、他の生産国のワインにおける”Barrique”や”Barrel fermentation”などに類するものとして使用されてきたのです。
土壌はワインの味を表現しない
ブドウの樹は根から土壌中のミネラルを吸い上げ、果実に蓄積していく。だからこそ、ワインにはそのブドウが育った土壌の味が表現される。
こうした解説は現在も広く耳にする機会があります。また、生産者がいる試飲会に参加したりすると、ブースのテーブルにワインと並んで畑の石が置かれている光景もしばしば見かけます。こうした経験は、土壌がワインの味を決定する重要な要因であるとの印象を強めがちです。
しかし、現在の科学的知見はこうした印象に対して慎重な姿勢を示しています。
土壌タイプがワインの官能特性に及ぼす影響については研究間で結果が一貫せず、包括的な科学的コンセンサスは形成されていません。ただし、より限定的な仮説である、ブドウの樹が土壌基質由来のミネラルを吸収し、その蓄積を通してワインに明確な官能特性を付与するという考えは科学的検証を通して否定されています。
土壌の差はその土地が所属する地域の気候的特徴などからも不可分です。このため土壌タイプの違うワインに感じる差異が本当に土壌の違いに基づくものなのかどうかは分からないのです。しかしそうした中でも、科学的検証の結果は土壌の違いよりもヴィンテージや生産者といった要素の方がより大きな影響力を示すことを示唆しています。
土壌タイプの差は、根の侵入深度や養分利用可能性、そして利用可能な保水水分量の違いなどによってブドウの生育状況に影響を及ぼす、間接的な影響を及ぼすものとして位置づけられています。
ワインの味を変える土壌の「名前」
実際の土壌タイプの違いはワインの味や香りに明確な差異をもたらさない一方で、ラベル上に書かれた土壌の「名前」はワインの味を変えるらしいことが指摘されています。
ドイツで4種類の土壌タイプ (Buntsandstein、Löß、Muschelkalk、Schiefer) から各5本ずつ、ワインを集めてラベル上の土壌タイプの表記がどのような影響をもたらすのかを検証する実験が行われました。集められたワインはいずれもブドウ品種はリースリングでしたが、その以外は生産地域も生産者も異なっており、ヴィンテージも2020年と2021年の2種類が混在しています。また検証は20名のワインの専門家に対して行われています。
この検証事例では、3つのステップに分けて実験が行われています。最初に各ワインが土壌タイプの情報を明らかにしないまま提供されました。これに続いて次は同じワインが今度は土壌タイプの情報を付記した形で提供され、最後は20種類すべてのワインが等量でブレンドされたワインが提示される土壌タイプの情報だけを変えて提供されています。被験者はそれぞれに対して提示された記述子に基づいて0から100点のスケールで評価し、その評価結果の違いから土壌タイプの情報の有無が官能評価にどのような影響を与えるのかが判断されました。
結果は明確でした。土壌タイプの情報が提示された場合とされなかった場合とで評価の結果に明確な違いが確認されたのです。また評価結果の変化には、土壌タイプごとにおおよそ一貫したパターンが見られたと報告されています。そしてそれらの変化はいわゆる「ミネラル」に関連した記述子においても見られました。
つまり、科学的な見地からは否定されている土壌タイプによるワインの味への影響は、実際の土壌タイプとは無関係にラベル上への土壌名の記載という視覚的情報によって生じていることが確認されたのです。
この検証はあくまでも専門家を対象に行われているため、一般消費者でも同様の結果や傾向が見られるかどうかは今後の検討課題として残されてはいます。しかし少なくとも一定の層においては、科学的知見と実際の知覚の間には隔たりがあることが示されたのです。
土壌名が決めるワインの味
この検証において特に大きな意味を持つ結果は、20種類すべてのワインを等量でブレンドしたワインに対して異なる土壌タイプの情報を付記した比較から得られたものです。
この検証パートでは事実上、同一のワインに対して4種類の異なる土壌タイプの名前が付記して提供されています。ワインに違いはないにもかかわらず、得られた官能評価の結果には有意差が存在しており、しかもその変化の傾向には検証全体を通して見られるパターンが存在していました。この結果からは、実際のワインからは独立したラベル上の土壌名が消費者の知覚に影響することが示唆されます。
検証を通して得られた傾向の1つとして、Schiefer (シーファー) の記載の影響が興味深い結果を見せています。Schiferとはスレート (Slate) のことで、ドイツでもMoselやNaheといった産地に特徴的な土壌タイプです。この記載を行ったワインでは総じてsourとflintyの記述子の点数が増加しています。単品ワインだけではなく、20種のブレンドワインでも同様の結果が示されました。
flintyとはよく火打ち石様の香りを表すために使用される記述子です。ところが地質学的にはflint (火打ち石) とslateはまったくの別物です。仮にブドウが土壌中のミネラルを吸収したり、土壌のタイプがワインの味に直接影響していたとしても、Schiefer土壌であることが示されてflintの味が出ることはありません。しかし実際の評価結果では、Schieferという情報が示されることで明確にflintの影響を感じられているのです。
土壌名という期待操作
地質学的にはまったくの別物である鉱物の存在を感じたり、同じワインであるにもかかわらずラベル情報が変わるだけでそれまで感じていた香りを感じなくなったりする評価結果は、土壌に関わる情報が引き起こす2つの可能性を示していると考えられています。
1つは土壌タイプに関する情報が提供されることでそこから期待される知覚に対する感度の上昇です。これは部分的には認知バイアスとしても説明されますが、予め存在するであろうと予想される対象を意識することで、その存在を感じやすくなっている可能性です。
過去に行われた別の検証事例でも、事前情報なしの自由記述では指摘されていなかった一部の香りが明示的に指示されることで認識されるようになったとする報告がなされています。
2点目は先行するイメージによる影響です。これは同化-対比理論で説明されます。
同化-対比理論とは、予め期待されるものと実際に知覚されたものとの乖離が小さい場合、知覚が期待方向にシフトする同化効果が生じる一方で、乖離が大きい場合には逆に期待から離れる方向に知覚が誇張される対比効果が発生することを説明した理論です。今回の事例では、各土壌タイプに対する先行イメージ (期待) と実際のワインの特徴との乖離が比較的小さかったため、同化効果が生じ、知覚が予め持っているイメージの方向にシフトした可能性が高いと考えられます。ブレンドワインでラベル表示を変えるだけで実際の官能評価結果が変化したことなどが、こうした影響の存在を示しているといえます。
こうした結果からいえることは、土壌名の表示は客観的情報提供ではなく、消費者に対する期待操作として機能する、ということです。そして同時に、そこには提供される情報に対する明確な先行イメージの存在が必要となります。実際にドイツで行われた検証においても、対象とした4つの土壌タイプのうち1つは被験者が明確な先行イメージを持っていなかったため、土壌情報を提示しても評価への明確な影響は生じませんでした。
ワイン造りに、あなたらしさを活かすパートナーを
栽培や醸造で感じる日々の疑問や不安を解消し、ワインの品質をさらに高めたい──
Nagi Winesは、あなたの想いとスタイルを尊重しながら、すべての工程をともに歩みます。
経験豊富な専門家が現場に入り、知識・技術・品質の向上を、実地作業を通じて支援。
費用を抑えつつも、あなたのワインらしさを守りながら確かなフォローを行います。
まずはお気軽にご相談ください。
ナラティヴとしての土壌タイプ
土壌タイプに関する情報が提供されることで想起されるイメージは、消費者が予め持っている特定のイメージに基づきます。一方で先行する明確なイメージが欠落している場合、仮に情報の提供があったとしてもそこからは特に影響は生じません。そしてそのイメージは、Schieferが地質学的には関係のないflintと関連付けられているように、事実の客観的伝達やその集積によって形付けられる必要は必ずしもありません。
こうした事実からは土壌タイプに関する情報をより効果的に使用するためには、予めその土壌タイプに期待してほしいイメージを用意し、定着させていくことが何よりも重要であることが理解されます。事実の単なる集積ではなく、ある特定の文脈の中で意味づけられるこうしたイメージの在り方は、まさに物語的なものといえます。物語が広く定着することで共同体内で共有される意味の体系化がなされるのです。物語的理解、つまりはナラティヴとして土壌を位置づけ、定着させることができれば、そのボトルのワインは実際にそうした味を感じられることになります。
土壌に関連する情報がナラティヴとして存在するのであれば、それは同時に土壌タイプによって感じる味わいの違いが自然科学的な事実ではなく、文化や歴史の中で形成された認識の産物であることを示唆します。ドイツにおけるSchieferやMuschelkalkの情報が提示されたワインに感じる味わいと、別の生産地域におけるslateもしくはlimestoneの表記がなされたワインに感じる味わいの傾向に違いがあるのもこれが理由と考えられます。
地質学的にはSchieferとslate、Muschelkalkとlimestoneは基本的に同じものです。そのため本質的にはこれらのワインの味わいには共通点があるはずです。しかし土壌タイプに紐付けられている先行イメージがナラティヴに依拠する場合はこの限りではありません。ナラティヴは基本的にその土地の文化的背景をもつ可能性が高く、それぞれの土地ごとに異なる内容のナラティヴが成立し得ます。土壌タイプから感じる味を規定するナラティヴが異なるのであれば、仮に地質学的には同一の土壌タイプであったとしてもそこから感じる味わいは変わり得るのです。
ドイツで行われた検証では被験者は全員がワインの専門家でした。そのため特に強固な先行イメージを持っていた可能性が高いことが予想されます。こうした状況からはそこまでワインに詳しくない一般消費者でも同様の傾向が見られるのかどうかは分かりません。一部の検証事例からは一般消費者であっても土壌タイプに対する先行イメージを保有している可能性が指摘されていますが、そうした状況がどの程度のバイアスを示すのかは現状では未知数です。
しかしそうした消費者であっても、ワインに関連した知識を得ていく中で徐々に既存のナラティヴに触れ、バイアスの程度を高めていく可能性は否定できません。
消費者にとっても生産者にとっても、土壌は土壌そのものではなく、そこに付帯するイメージにこそより大きな価値があることをこの調査は明らかにしています。